目次
- 1 血栓を作らない食事法を
- 1.1 なすで血圧を改善していく
- 1.2 血管対策に必須のしょうが
- 1.3 糖質が少ない里芋を
- 1.4 こんにゃくでヘルシーに腸活を
- 1.5 きのこでインスリンを活発化
- 1.6 血糖値を安定させてくれる海藻
- 1.7 ブルーベリーで毛細血管を強く
- 1.8 りんごを皮ごと食べて血圧管理
- 1.9 血管をしなやかに保つみかん
- 1.10 マグネシウムが豊富なバナナを
- 1.11 中性脂肪を抑えるアボカド
- 1.12 キウイで体のさびを食い止める
- 1.13 栗のタンニンが血管に作用
- 1.14 間食ナッツで血糖値を安定させる
- 1.15 ゴマの独自の成分で血圧対策
- 1.16 高カカオチョコで血流改善
- 1.17 ブラックコーヒーで血糖値を減少
- 1.18 緑茶で血管の老化を対策
- 1.19 スパイスで簡単に血管ケアを
- 1.20 ハーブをプラスして血管を労る
- 2 まとめ
血栓を作らない食事法を
血栓を作らない食事のポイントになるのが、血圧、血糖、コレステロールを日々コントロールしていくことになります。
このことを少しずつ意識していくだけで、血管、血液、血流の改善へと繋がり、負担が減っていき血栓ができにくい血管環境になるのです。
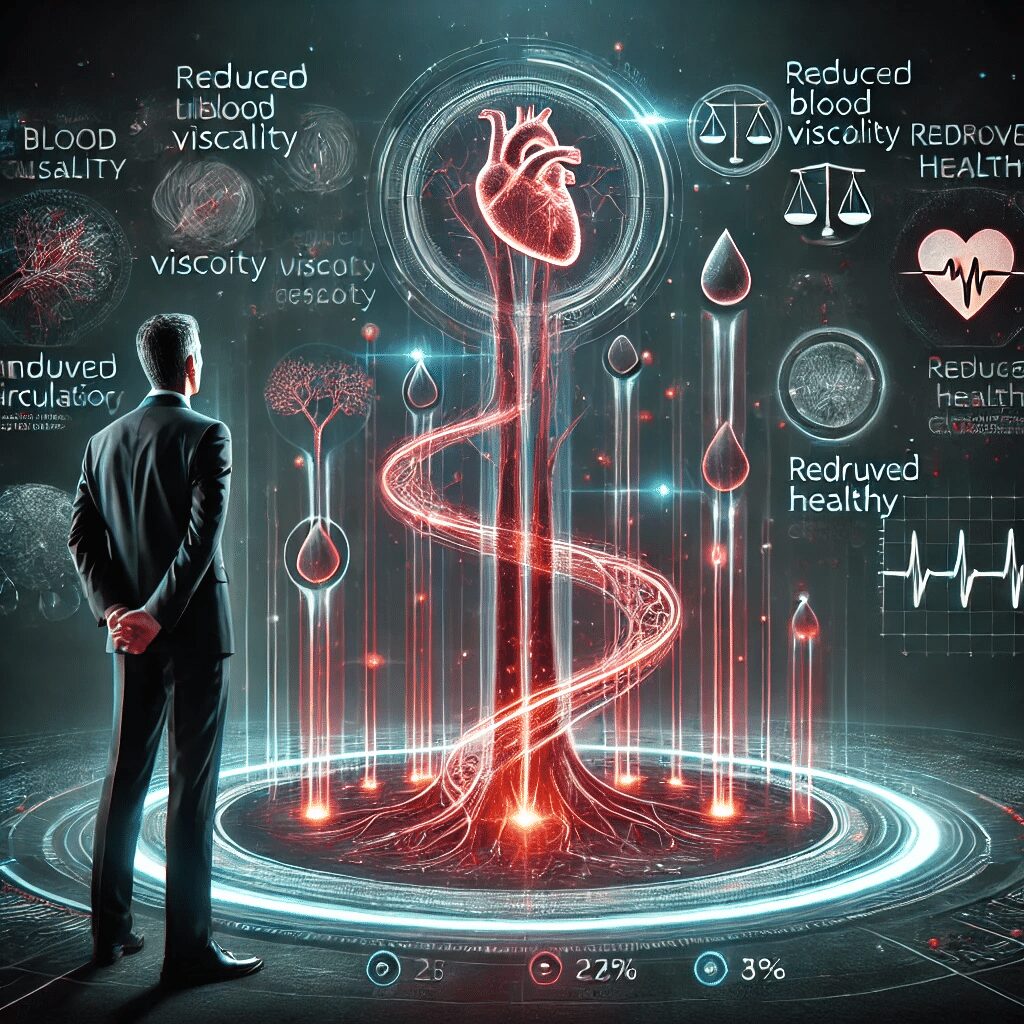
血管系を今日から整えていくことで、体の隅々に栄養、酸素が行き渡るので、免疫力も上がり不調知らずの日々を送ることにも繋がるので、ぜひ血栓改善食材を

なすで血圧を改善していく
なすは血圧を安定させる効果が期待できる、優れた野菜のひとつで、皮の部分に含まれる「ナスニン」というポリフェノールには、強い抗酸化作用があり、血管を傷つける活性酸素を除去し、しなやかさを保つ働きがあります。
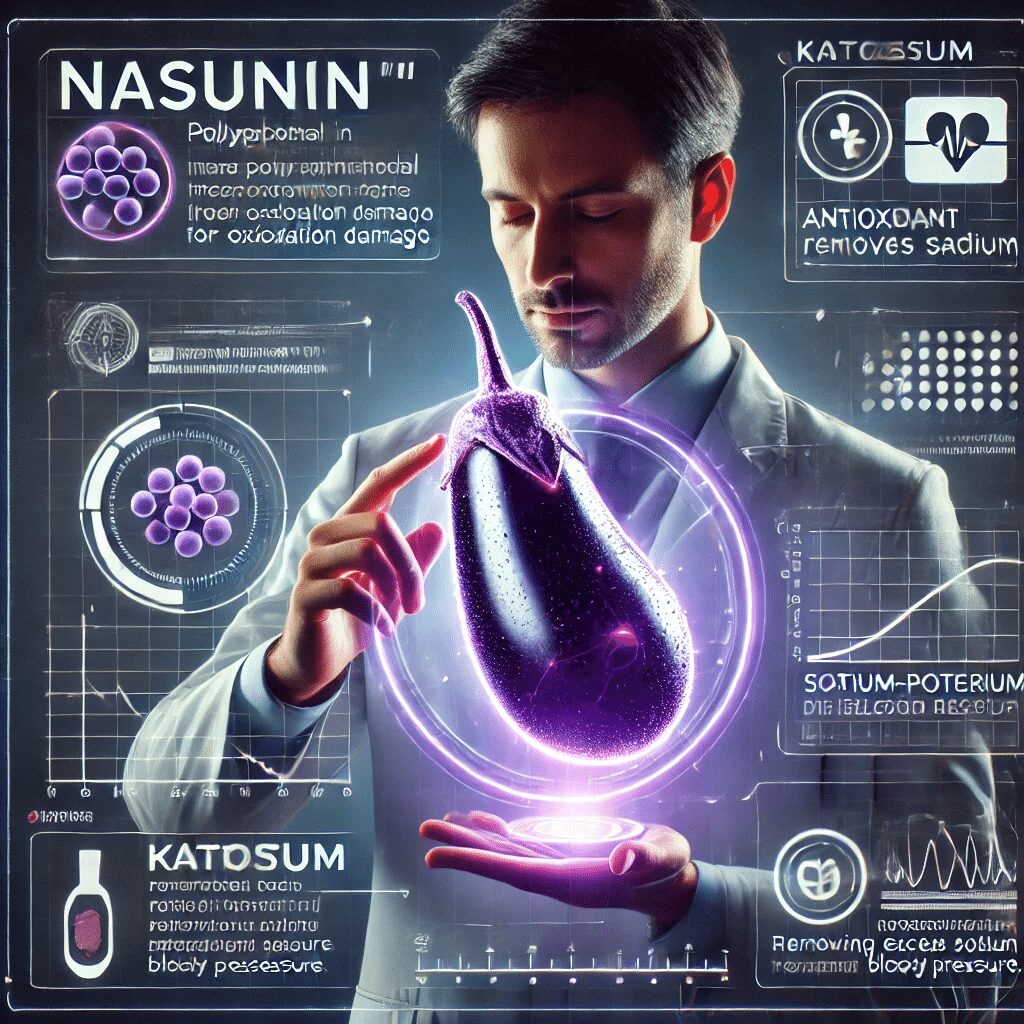
また、なすにはカリウムも豊富に含まれており、体内の余分なナトリウム(塩分)を排出してくれ、塩分の摂りすぎが気になる現代人には、なすのようなカリウムが多い野菜を積極的に取り入れることが勧められます。
油との相性も良いので、炒め物や揚げ物にしても美味しく食べることができ、焼きなすや煮浸しなどにして食卓に取り込みましょう。
 |
血管対策に必須のしょうが
しょうがは古くから健康維持に使われてきた万能食材で、血管対策にも非常に有効です。
しょうがに含まれる「ジンゲロール」や「ショウガオール」といった成分には、血管を拡張し血流を促す働きがあり、血圧が安定し、動脈硬化や冷え性の予防につながります。

また、しょうがには強い抗炎症作用もあり、血管内の炎症を抑えてくれるため、血管の老化や詰まりを防ぐ役割も期待でき、体を温める作用もあるため、寒い季節や冷え症の方は積極的に取り入れたい食材です。
生よりも加熱や乾燥させたしょうがのほうが、血行促進効果は高まるので、自分にあったしょうがの取り入れ方を見つけていきましょう。
 |
糖質が少ない里芋を
里芋は芋類の中でも比較的糖質が少なく、血糖値を気にする人にとって取り入れやすい食材です。
他の芋に比べてカロリーも低く、食物繊維が豊富に含まれているため、糖の吸収を穏やかにし、血糖値の急上昇を抑える効果が期待できるのです。
さらに、ぬめり成分であるガラクタンには、腸内環境を整える働きや、免疫力アップ、胃腸の保護といった健康効果もあり、ビタミンB群やカリウムも含まれているので、血圧の安定にも効果を発揮してくれます。
こんにゃくでヘルシーに腸活を
こんにゃくは、低カロリーで食物繊維が豊富な理想的な腸活食材で、「グルコマンナン」という水溶性食物繊維は、腸内で水分を吸って膨らみ、便のかさを増やして排出をスムーズにします。
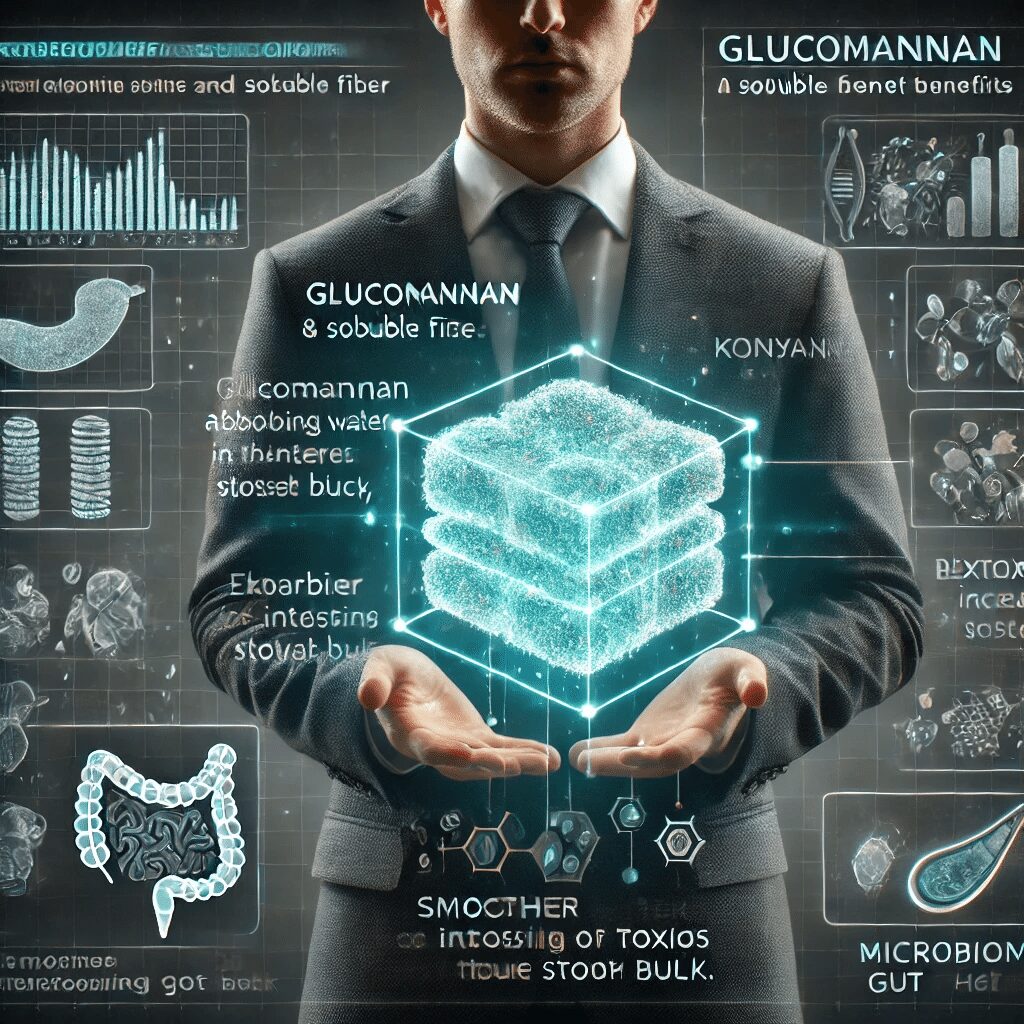
これにより、腸内に溜まった老廃物や毒素の排出が促され、腸内環境の改善につながるのです。
また、こんにゃくは噛みごたえがあり、自然と食事の時間が長くなって満腹感を得やすく、過食の防止にも役立ち、糖質や脂質が少ないため、ダイエット中や糖質制限中の方に非常におすすめ食材になります。
きのこでインスリンを活発化
きのこ類は、カロリーが低く栄養価が高いことから、糖尿病予防や血糖値対策に最適な食材として注目されています。
きのこに含まれる「β-グルカン」という水溶性食物繊維には、血糖値の上昇を緩やかにする働きがあり、食後高血糖を防ぐうえで非常に有効です。
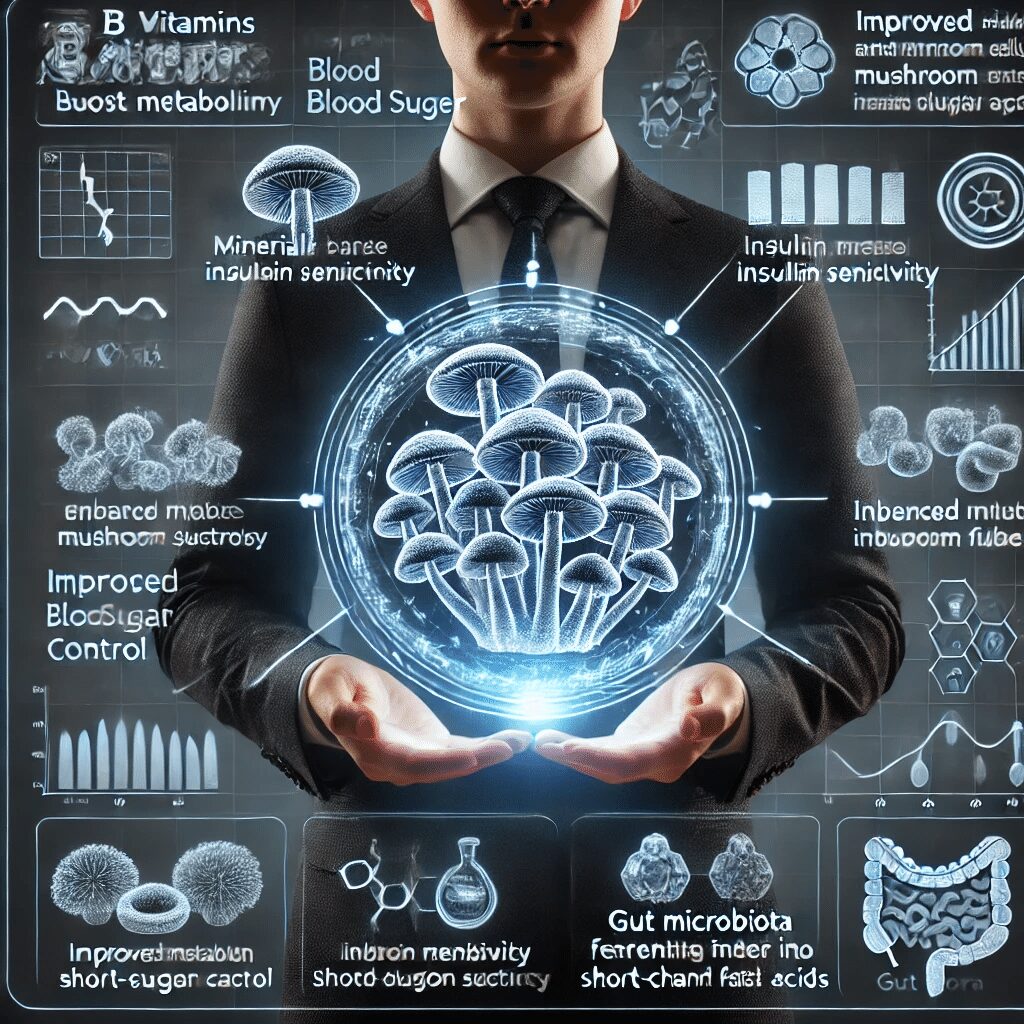
また、きのこは血糖を下げるホルモン「インスリン」の働きを助ける効果も期待できます。
きのこに含まれるビタミンB群やミネラル成分、抗酸化物質が代謝を促し、インスリンの感受性を高めることで、細胞がブドウ糖を取り込みやすく、体がインスリンに反応しやすくなり、血糖値のコントロールがしやすくなるのです。
さらに、きのこは腸内環境の改善にも役立ちます。腸内細菌がきのこの食物繊維をエサにすることで短鎖脂肪酸を生み出し、代謝や血糖コントロールにも良い影響を与えてくれます。
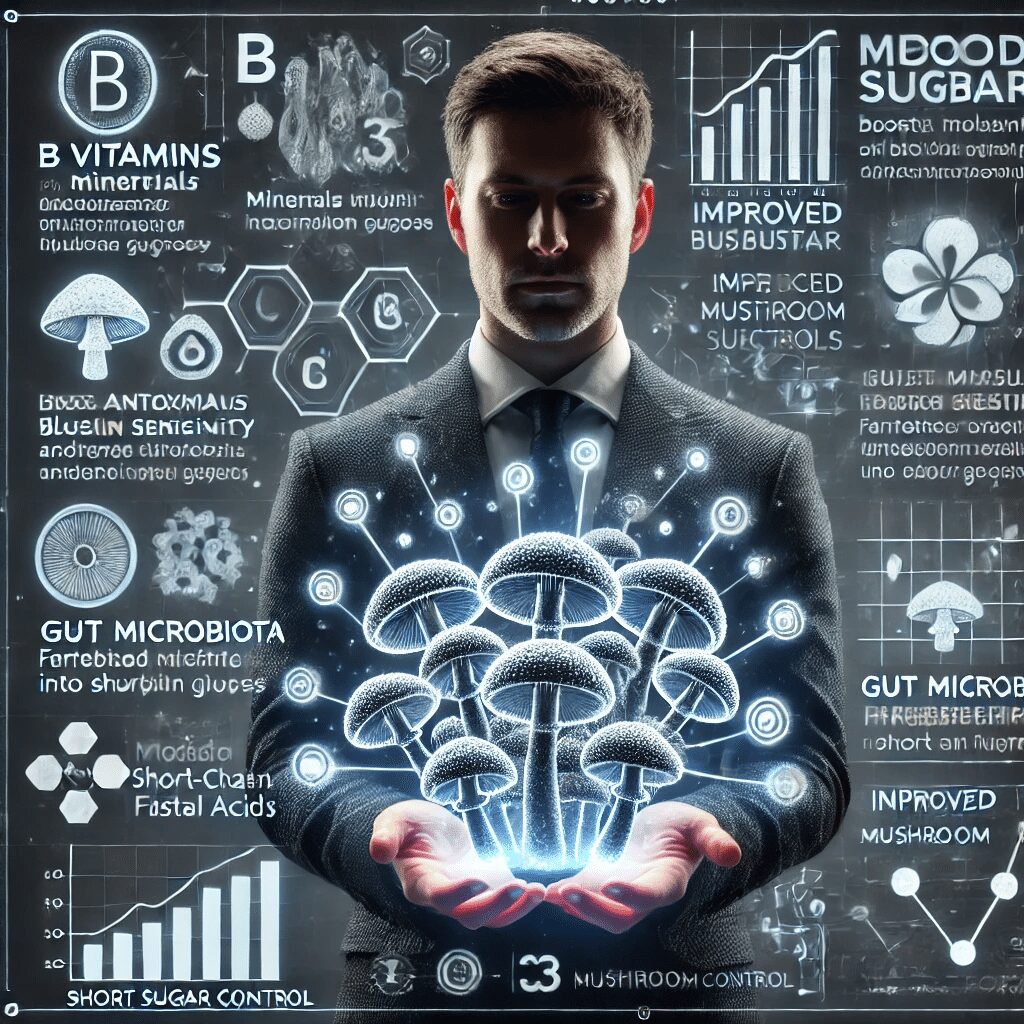
しいたけ、えのき、しめじ、まいたけなど、種類も豊富で調理のバリエーションも広く、炒め物やスープ、和え物などに加えることで、インスリンの働きをサポートし、血糖値を整えたい方にとって、毎日でも食べたい優秀な食材です。
 |
血糖値を安定させてくれる海藻
海藻は、血糖値を安定させるために役立ち、わかめ、ひじき、昆布、もずくなどに豊富に含まれる水溶性食物繊維(アルギン酸やフコイダン)は、食後の糖の吸収をゆるやかにし、血糖値の急上昇を防ぎます。
これにより、インスリンの過剰分泌が抑えられ、血糖のコントロールがしやすくなります。
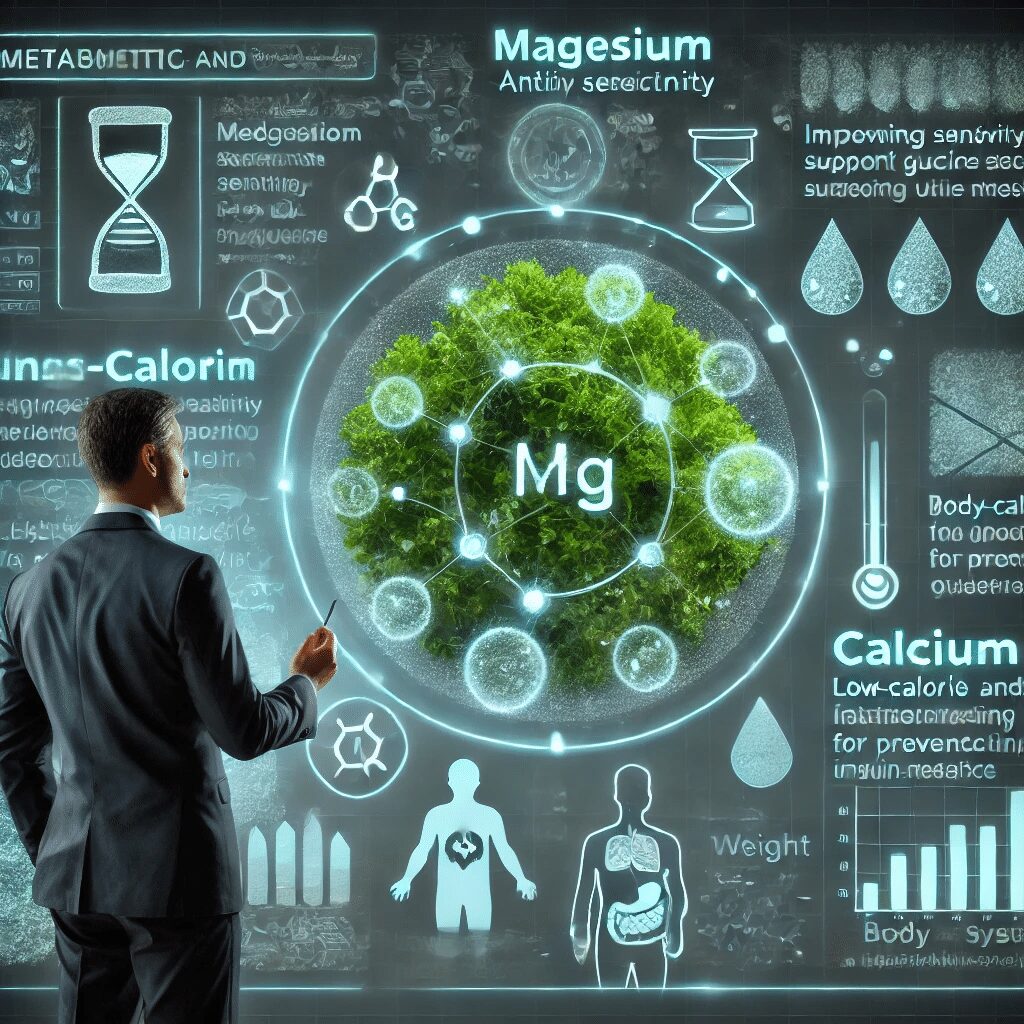
また、海藻に含まれるマグネシウムやカルシウムは、インスリンの感受性を高める作用があるとされ、糖代謝の働きをサポートします。
さらに、海藻には低カロリーで満腹感があるという特長もあり、食べ過ぎを防ぎ、肥満やインスリン抵抗性の予防にもつながります。
食事の最初に酢の物やスープで海藻を取り入れると、血糖値の上昇を抑える“ファーストアプローチ”にもなり、非常に効果的な食材になってくれるのです。
ブルーベリーで毛細血管を強く
ブルーベリーは、見た目の可愛らしさだけでなく、健康効果の面でも非常に優れた果物で「アントシアニン」という色素成分には、抗酸化作用があり、血管、特に毛細血管を丈夫に保つ働きがあるとされています。
毛細血管は全身に酸素や栄養を運ぶための大切な通り道ですが、加齢やストレス、生活習慣の乱れによって傷つきやすくなります。
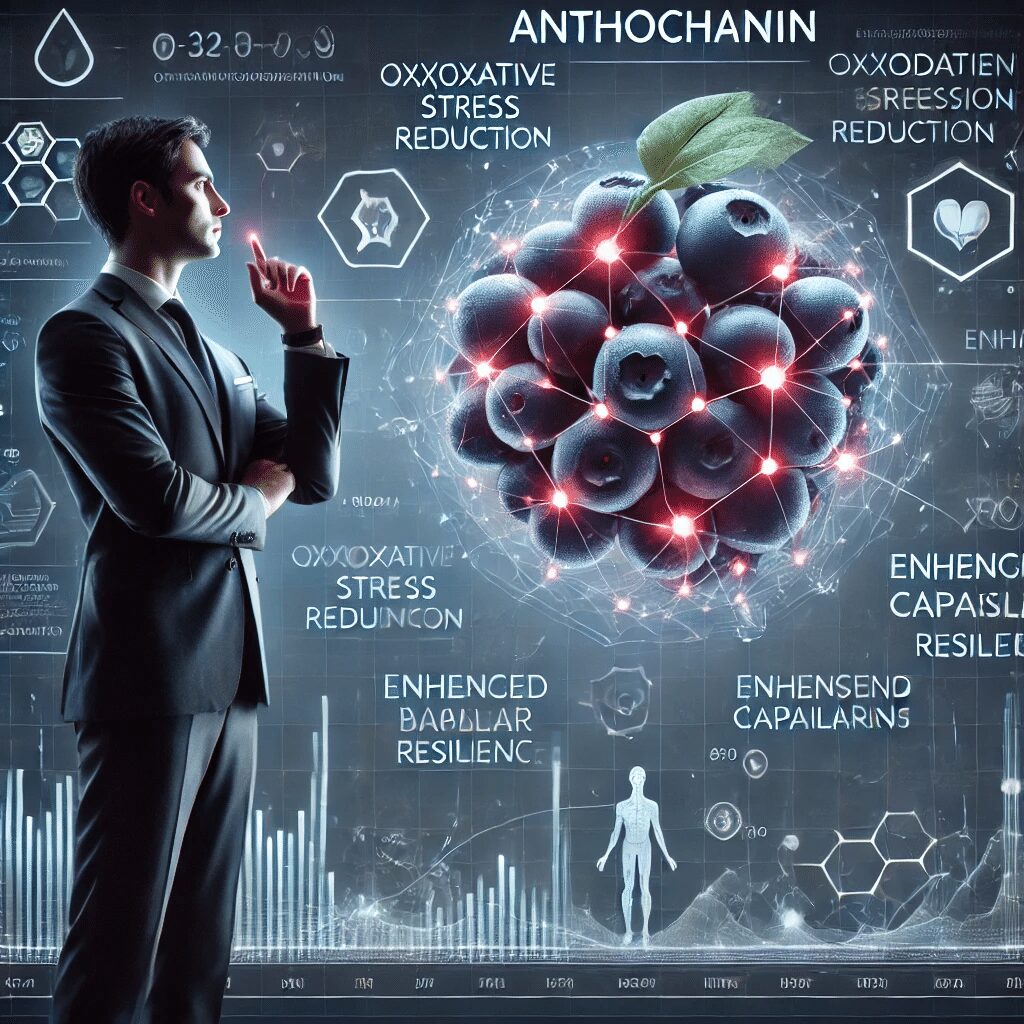
毛細血管が壊れると、血流が滞り、冷えやむくみ、肌荒れ、視力低下、さらには脳や心臓の機能低下にもつながってしまいます。
そこで役立つのがブルーベリーに含まれるアントシアニンです。血管の内皮細胞を守り、毛細血管の弾力性や強度を保つことで、全身の健康を守ってくれるのです。
また、ブルーベリーにはビタミンCやビタミンE、食物繊維も豊富に含まれており、抗酸化・抗炎症作用の相乗効果も期待できます。
 |
りんごを皮ごと食べて血圧管理
りんごは「1日1個で医者いらず」と言われるほど健康効果が高い果物、皮に含まれるポリフェノール「プロシアニジン」や「ケルセチン」。
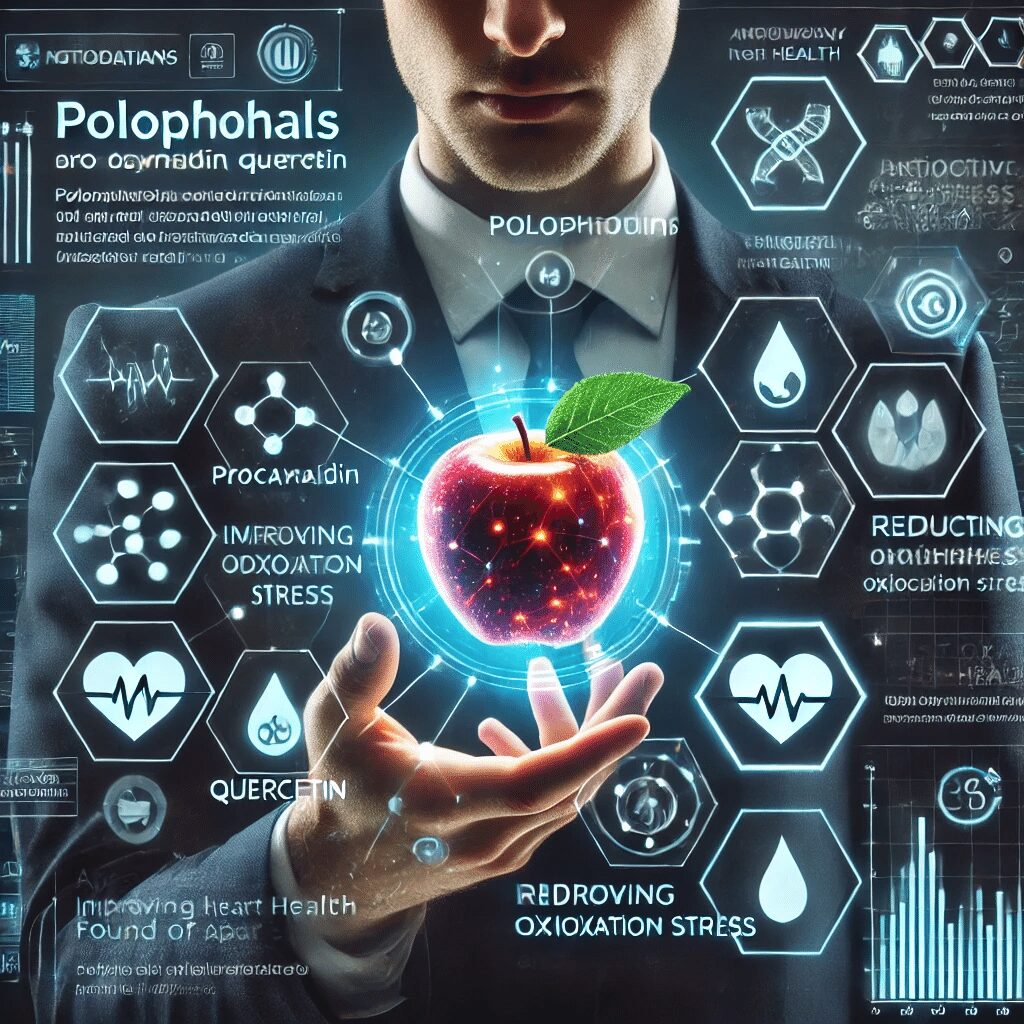
これらには血管の炎症を抑え、血圧の上昇を防ぐ作用があり、皮には水溶性食物繊維のペクチンも豊富に含まれ、腸内環境を整え、余分な塩分や脂肪の排出にも役立ちます。
りんごは果肉だけでなく、皮ごと食べることでその栄養価を余すことなく取り入れることができるので、皮の農薬が気になる場合は、よく洗ったり、無農薬りんごを選び、皮ごとりんごを取り入れてみましょう。
 |
血管をしなやかに保つみかん
冬の定番果物みかんは、血管の健康を守る優れた栄養源、みかんに含まれる「ヘスペリジン」というポリフェノールは、果皮や薄皮に多く含まれ、毛細血管を強くし、血流を改善する作用があります。
さらに、ビタミンCも豊富で、抗酸化作用により血管の老化や炎症を防ぎ、しなやかさを保つのに役立ちます。
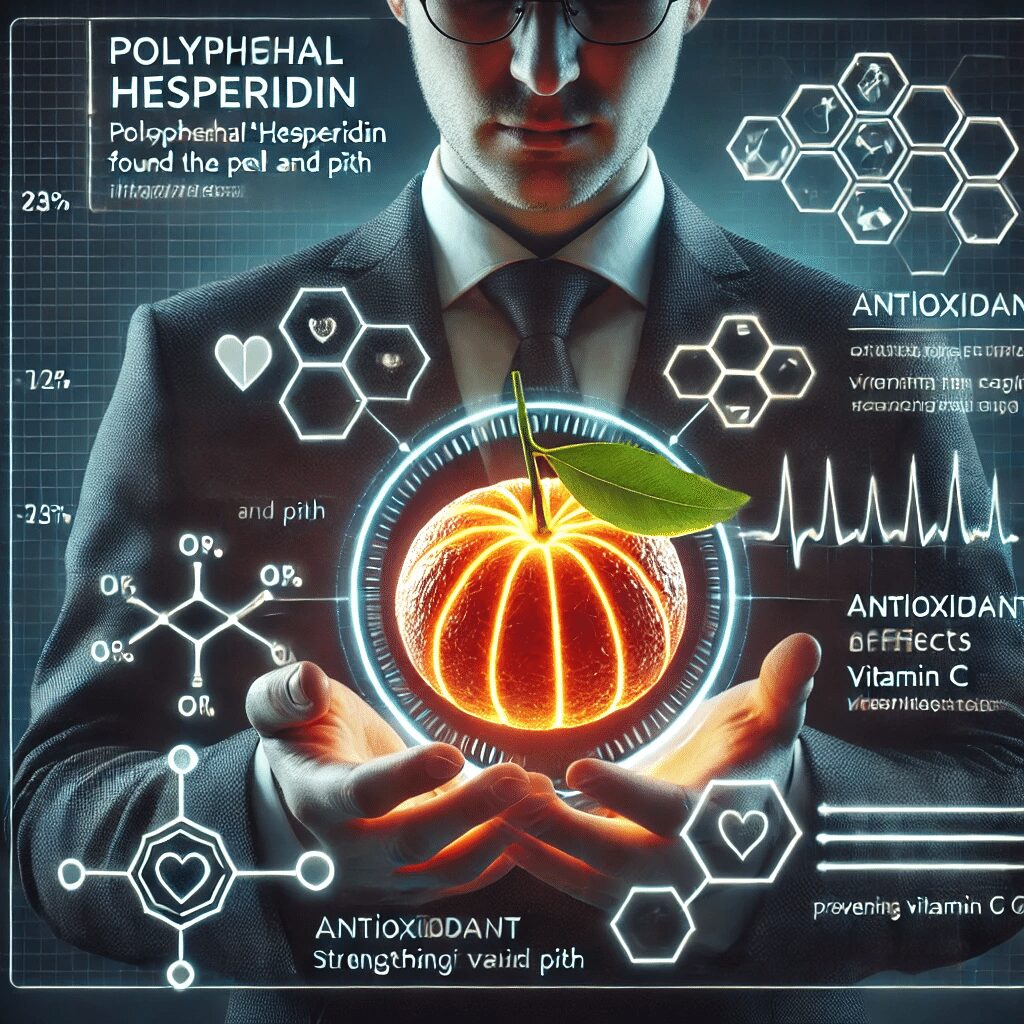
また、みかんには食物繊維も適度に含まれており、腸内環境を整えることで、全身の代謝にも良い影響を与えます。
みかんは皮をむくだけで手軽に食べられ、薄皮ごと食べていき、血管のしなやかさを保ちましょう。
マグネシウムが豊富なバナナを
バナナはエネルギー補給に優れた果物として知られていますが、血管の健康にも貢献する「マグネシウム」が豊富に含まれています。
マグネシウムは血管を柔らかく保ち、血圧の安定や血流改善に不可欠なミネラルで、現代人に不足しがちな栄養素の一つです。
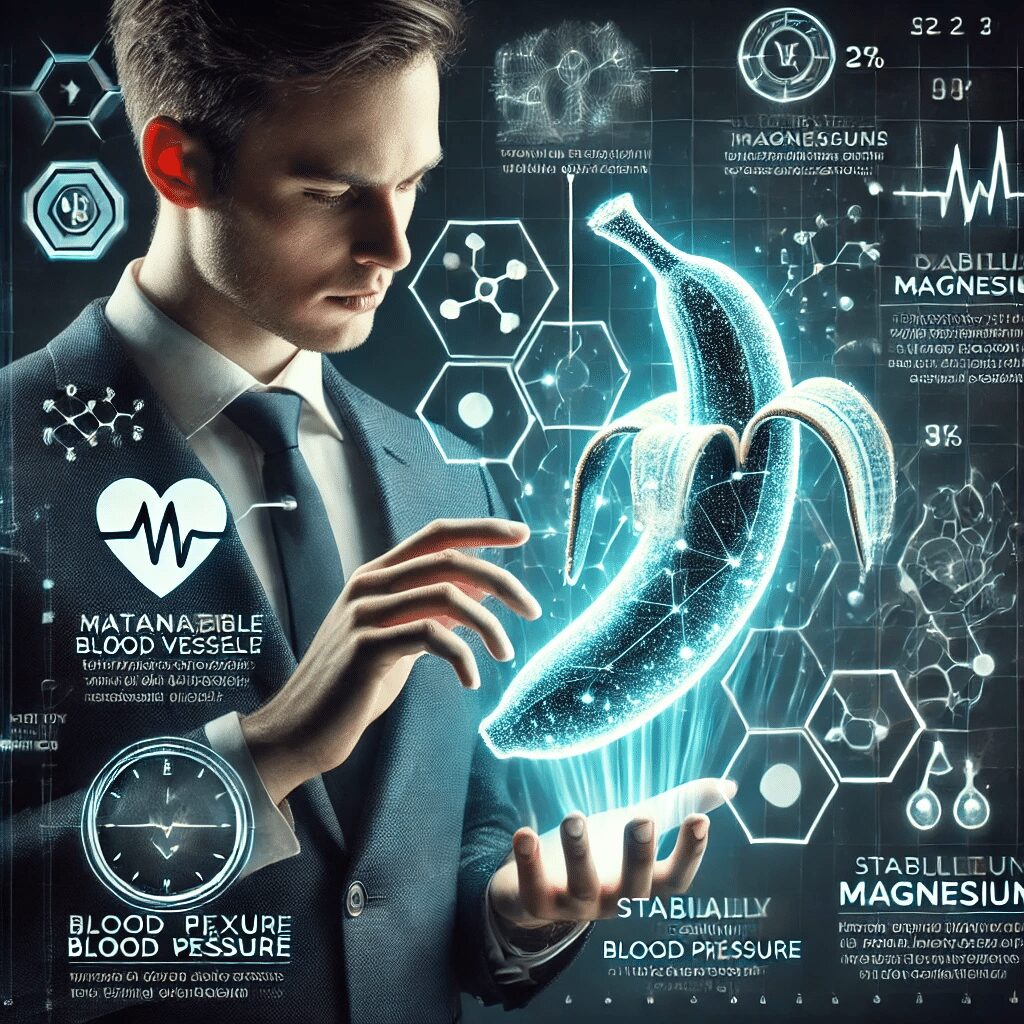
バナナを1本食べるだけで、1日に必要なマグネシウムのおよそ1割を手軽に補うことができます。
また、バナナは自然な甘さと食物繊維によって、血糖値の上昇を緩やかにする働きも期待できます。
朝食や間食にバナナを取り入れることで、エネルギーとともに血管にやさしい栄養をチャージでき、皮をむくだけで食べられる手軽さも大きな魅力な食材です。
 |
中性脂肪を抑えるアボカド
アボカドは中性脂肪の抑制に役立つ食材として注目され、脂肪分が多いイメージがありますが、その多くは「オレイン酸」などの不飽和脂肪酸で、血中の中性脂肪や悪玉コレステロールを下げ、善玉コレステロールを保つ働きをもたらします。
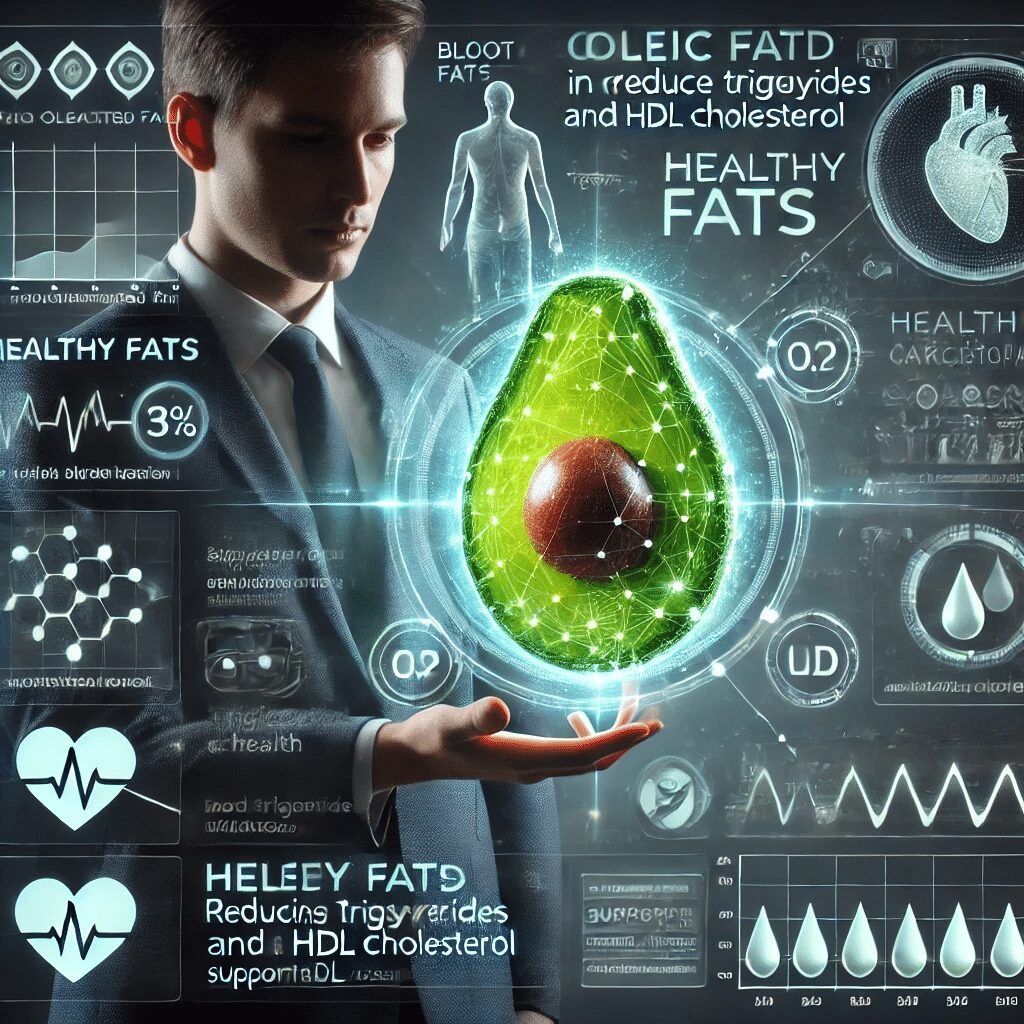
さらに、アボカドには食物繊維やビタミンE、カリウムが豊富に含み、腸内環境を整えてくれ、抗酸化作用で血管の老化を防いだり、余分な塩分を排出することで血圧を安定させたりと、全身の代謝バランスを整える力も持っているのです。
キウイで体のさびを食い止める
キウイは、体の「さびつき」を防ぐ抗酸化力に優れた果物、豊富に含まれるビタミンCは、活性酸素による細胞のダメージを抑え、老化や生活習慣病の予防に役立ちます。
1個のキウイには1日に必要なビタミンC量がほぼ含まれており、毎日の習慣に最適です。
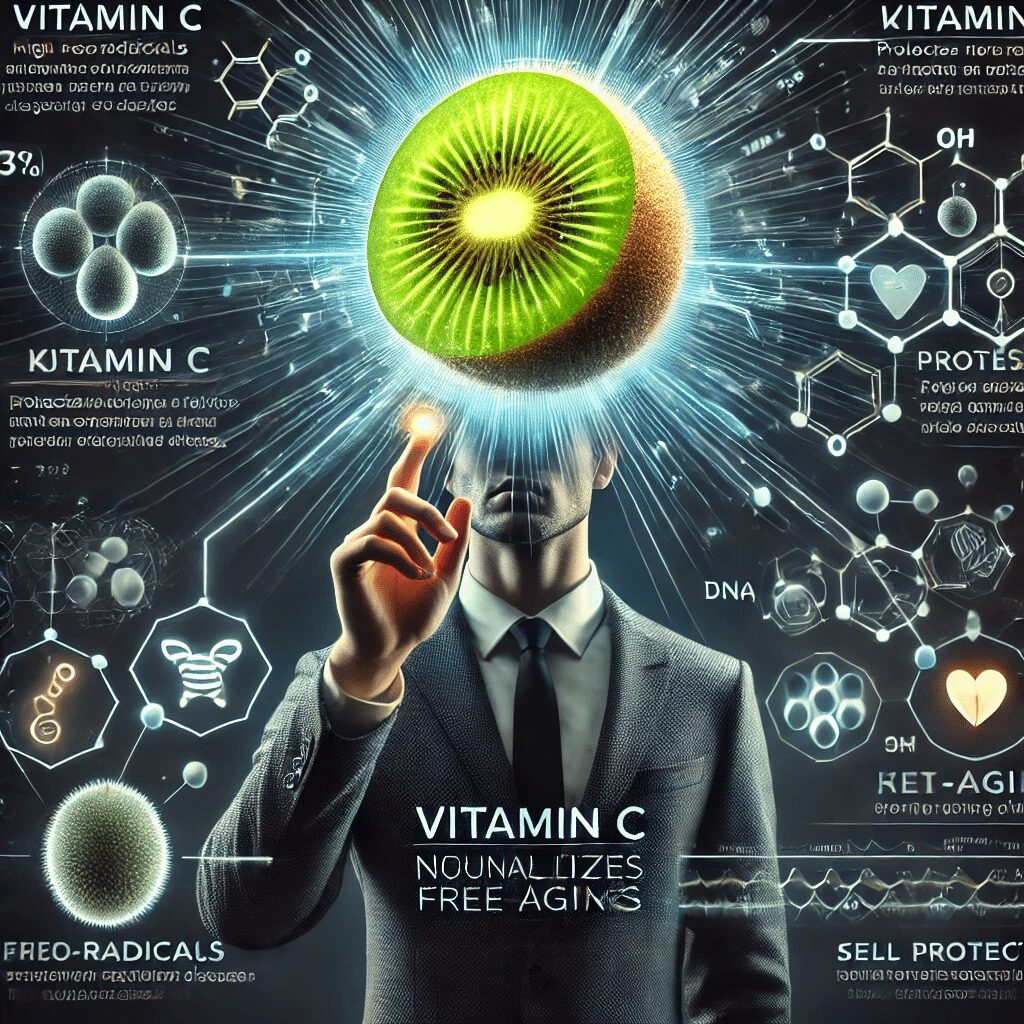
さらに、ビタミンEやポリフェノールも含まれ、血管のしなやかさを保つ働きも期待でき、水溶性・不溶性の食物繊維がバランスよく含まれているため、腸内環境の改善にも効果的です。
朝食や間食に手軽に取り入れられ、酸味と甘みのバランスも良く、飽きずに続けられるキウイで、体内の酸化を防ぎ、若々しい体を守っていきましょう。
栗のタンニンが血管に作用
栗にはポリフェノールの一種である「タンニン」を豊富に含み、この成分が血管の健康に大きく貢献します。
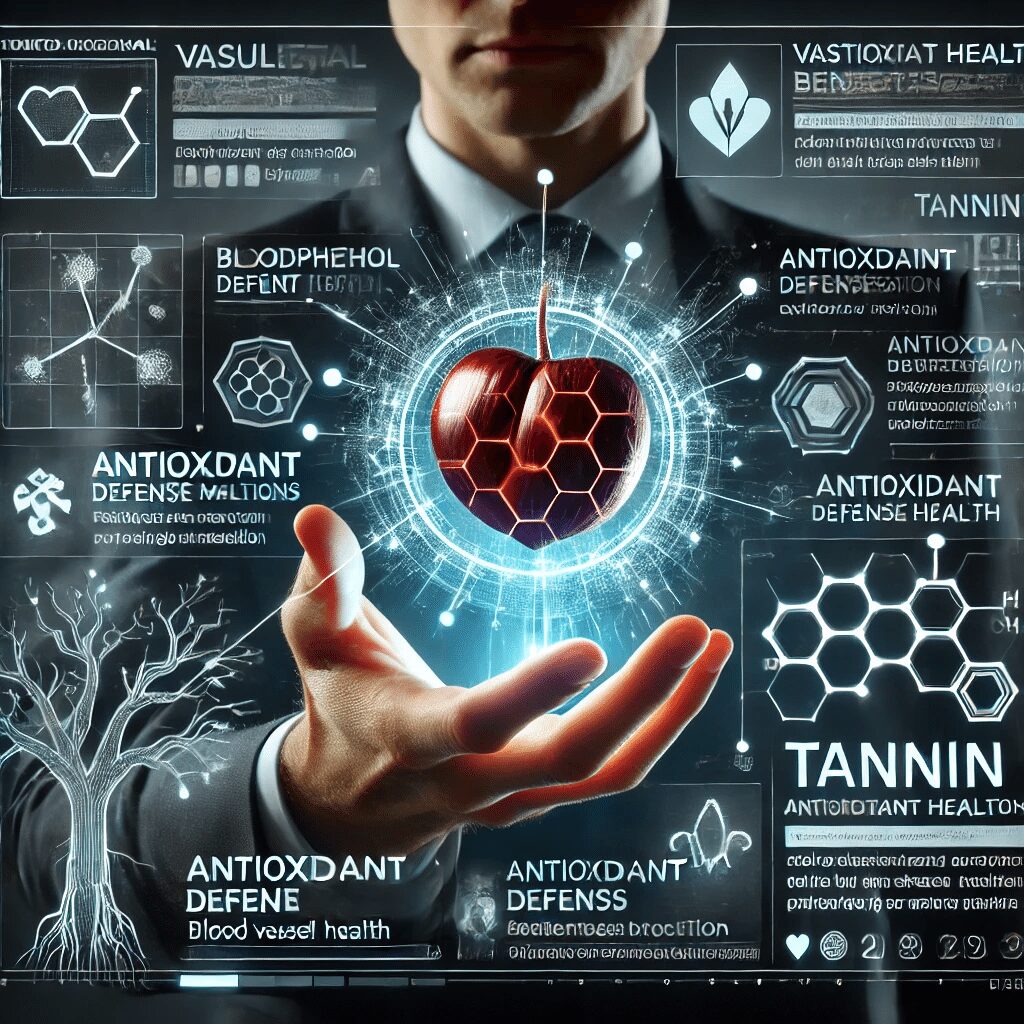
タンニンには高い抗酸化作用があり、血管内の活性酸素を除去して、血管のしなやかさを保ち、動脈硬化の進行を防ぎ、血栓のリスクも抑えることができるのです。
さらに、栗は脂質は少なめで食物繊維も豊富なため、血糖値の急上昇を抑える作用も期待できます。
間食ナッツで血糖値を安定させる
ナッツ類は、血糖値を安定させるのに非常に優れた間食で、アーモンド、くるみ、カシューナッツなどに含まれる不飽和脂肪酸や食物繊維、マグネシウムは、食後の急激な血糖値上昇を抑える働きがあります。
糖質の吸収を緩やかにし、インスリンの分泌バランスを保つことができるため、糖尿病予防にもつながってくれます。

ナッツは低GI値(グリセミック・インデックス)食材になり、血糖値に与える影響が小さいため、空腹時のおやつとしても安心で、ナッツはよく噛んで食べることで満足感が高まり、過食の防止にも役立ちます。
ただし、ナッツは高カロリーなので、1日あたりひとつかみ(約25〜30g)を目安に摂取し、無塩・素焼きのものを選ぶことで、余分な塩分や油分の摂取を避けることができます。
 |
ゴマの独自の成分で血圧対策
ゴマには「セサミン」や「セサモール」などのゴマ特有の成分が含まれており、これらが血圧のコントロールに効果を発揮します。

セサミンは強力な抗酸化作用を持ち、血管内皮の健康を保つことで血管の柔軟性を維持し、高血圧を予防する働きをもたらし、悪玉コレステロールの酸化を防ぎ、動脈硬化の進行も抑えるとされています。
さらに、ゴマにはカルシウムやマグネシウム、カリウムなどのミネラルも豊富に含まれており、これらも血圧調整に欠かせない栄養素です。
高カカオチョコで血流改善
高カカオチョコレートには、血流を改善するカカオポリフェノールを豊富に含み、強力な抗酸化作用を持ち合わせ、血管の炎症を抑えて柔軟性を保ち、血液の流れをスムーズにしてくれます。

また、血小板の凝集を抑制、血栓の予防にもつながり、高カカオチョコは糖質が少なく、血糖値の急上昇を防ぐことができるため、間食としても非常に優秀な食材です。
目安として1日10〜20gほどを習慣的に取り入れることで、冷えや肩こりの改善、集中力の維持にも好影響が期待でき、健康的な血流環境を整えるために、甘すぎない高カカオチョコをうまく活用しましょう。
 |
ブラックコーヒーで血糖値を減少
ブラックコーヒーには、血糖値の上昇を抑える働きがあるとされ、コーヒーに含まれるクロロゲン酸というポリフェノールには、糖の吸収をゆるやかにし、食後の血糖値の急激な上昇を防ぐ効果が期待できます。
ブラックで飲むことで、余分な糖分や脂肪分を加えることなく、健康的にその恩恵を得ることができ、クロロゲン酸には抗酸化作用もあり、血管の老化防止にも役立ちます。
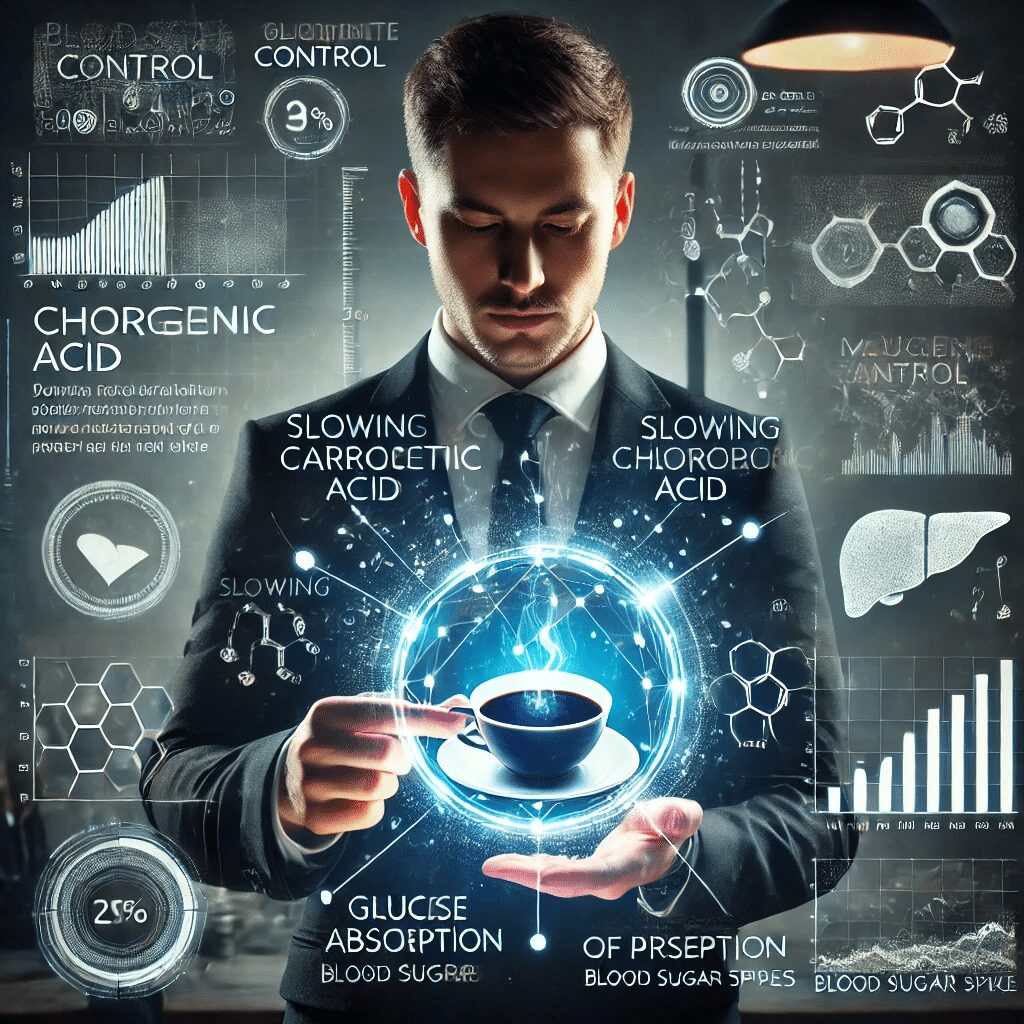
ただし、飲みすぎには注意が必要で1日2〜3杯程度が目安にしていき、ブラックコーヒーを取り入れる習慣は、糖質過多になりやすい現代の食生活において、手軽で効果的な血糖値対策となります。
カフェインが苦手な方は、ノンカフェインのコーヒーでもクロロゲン酸の効果が得られることが多いため、無理なく続けることができます。
緑茶で血管の老化を対策
血管の老化は、動脈硬化や高血圧、心筋梗塞などの重大な病気に直結、その老化を防ぐ味方のひとつが、日常的に親しまれている「緑茶」です。
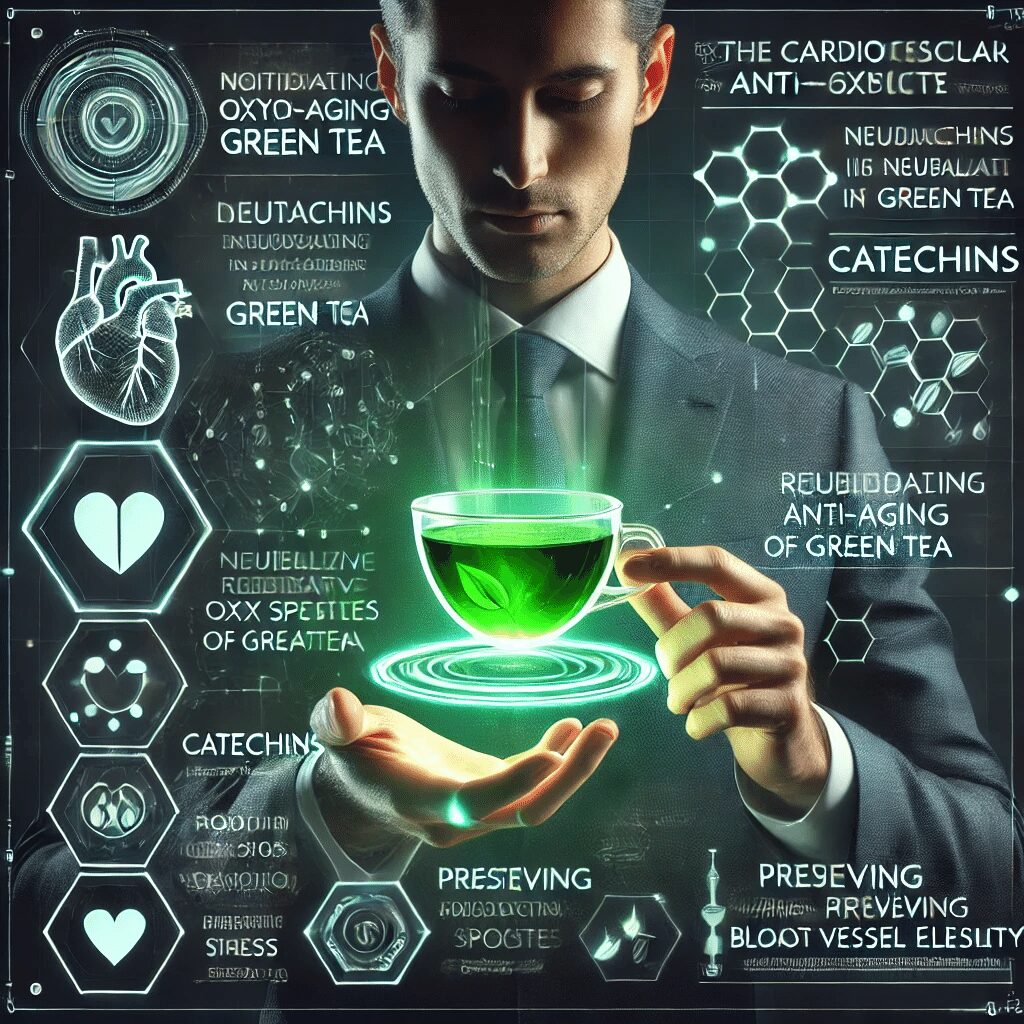
緑茶に含まれるカテキンは強い抗酸化作用を持ち、血管内の活性酸素を除去してくれる働きがあり、活性酸素が減ることで、血管のしなやかさを保ち、動脈硬化の進行を遅らせることが期待されます。
さらに、カテキンには悪玉コレステロール(LDL)の酸化を抑える作用に加え、血液をサラサラに保つ効果もあり、食後に1杯の緑茶を飲む習慣をつけるだけで、血管を若々しく保つサポートになります。
 |
スパイスで簡単に血管ケアを
スパイスは香りづけだけでなく、健康への効果が高いことでも注目され、血管の健康を守るために役立つスパイスは数多くあり、毎日の食事に少し加えるだけで、血流の改善や動脈硬化予防などが期待できるのです。
たとえば「ターメリック(ウコン)」は、肝臓を守るだけでなく、クルクミンという成分が持つ抗炎症作用や抗酸化作用によって、血管内皮のダメージを防ぎ、血管の老化を抑える働きがあります。
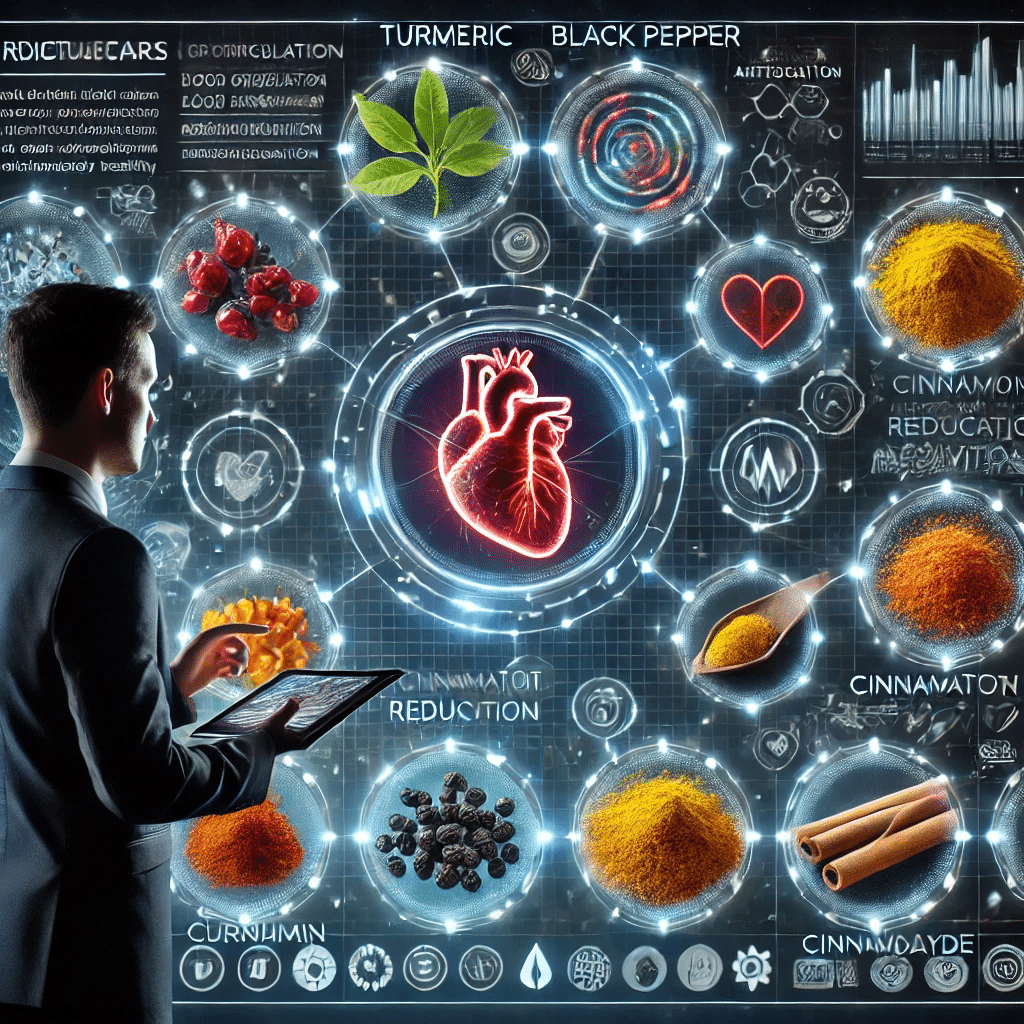
また、「シナモン」には血糖値を安定させる作用があり、糖による血管のダメージを軽減することで、動脈硬化の予防にもつながります。
「クミン」や「ガーリックパウダー」なども、抗酸化作用や抗炎症作用に優れ、血管の健康維持に効果的です。
スパイスは一度にたくさん摂る必要はなく、炒め物やスープ、温かい飲み物に少し加えるだけで十分で、塩分の変わりにスパイスをアクセントとして重宝し、減塩を自然にサポートしてくれます。
 |
ハーブをプラスして血管を労る
血管の健康を守るためには、日常の食生活の中で無理なく続けられる工夫が大切です。
その中でも、ハーブを取り入れることは、手軽で効果的な方法のひとつになり、ハーブには抗酸化作用や抗炎症作用を持つ成分が豊富に含まれ、血管の老化や炎症を防ぐ助けとなります。
たとえば「ローズマリー」には、カルノシン酸やロスマリン酸といった成分が含まれ、血管内皮を保護し、血流を促す作用があります。
また「タイム」や「セージ」も抗酸化作用に優れており、動脈硬化を予防するために役立ち、「バジル」は血液循環を改善し、冷えや高血圧のケアにも一役買います。
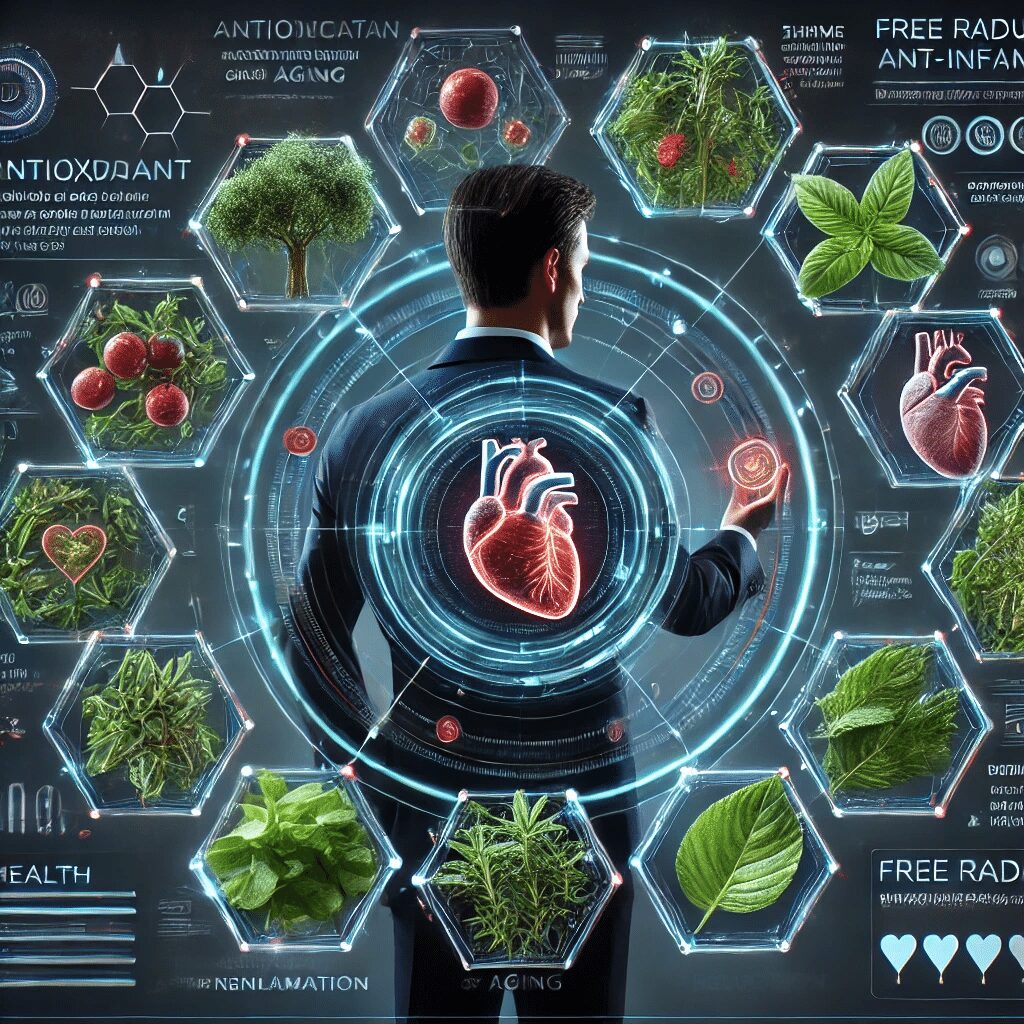
「オレガノ」や「ミント」などのハーブには、腸内環境を整える効果もあり、腸と血管の健康を同時にサポートし、腸内環境が整えば、炎症を起こしにくい体質に近づき、全身の血管への負担も軽減されるのです。
ハーブは生でも乾燥でも使え、サラダやスープ、炒め物、ハーブティーなど、さまざまな形で日常に取り入れやすいのが魅力ですので、料理のアクセントになるだけでなく、減塩効果にもつながり、味をしっかり引き出しながら健康を支えてくれます。
 |
まとめ
私たちの身近な食材には、血管や血圧、血糖値を整える大きな力があり、なすに含まれるナスニンやカリウムは抗酸化と塩分排出を助け、しょうがの成分は血流促進と抗炎症作用を発揮します。
里芋やこんにゃく、きのこ、海藻といった低カロリー・高食物繊維の食材は、血糖値の急上昇を防ぎ腸内環境を整えます。
ブルーベリーやりんご、みかんなどの果物に含まれるポリフェノールやビタミンは、毛細血管や血圧管理に有効です。
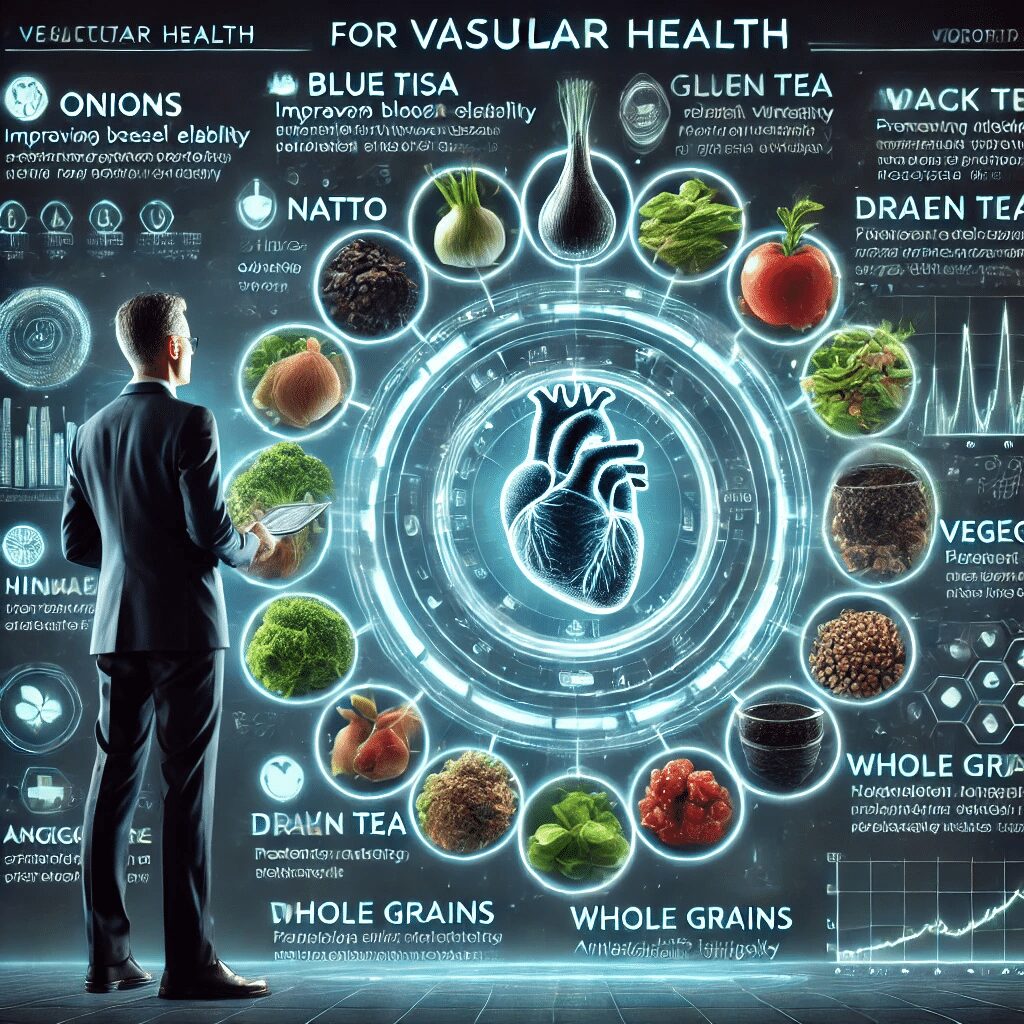
さらに、バナナやアボカド、キウイ、栗、ナッツといった食材も、ミネラルや良質な脂質で血管を柔らかく保ち、中性脂肪や酸化ストレスを抑えます。
ごま、高カカオチョコ、コーヒー、緑茶といった嗜好品も適量なら血流改善に役立ちます。
最後に、スパイスやハーブを日常に取り入れることで減塩効果も得られ、料理を楽しみながら血管を守ることができます。
これらを組み合わせ、無理なく食生活に取り入れることが、血圧と血糖値を安定させ、健康寿命を延ばしていきましょう。

最後まで見ていただきありがとうございました。
↓終活で分からない事や迷子になったら↓
このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています
LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV
インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/
アマゾンで本を出品しています

 |
- 【無意識に老化を進める習慣】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【食で体を保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【心を保つ習慣を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【習慣で革命を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【生涯健康体】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

31


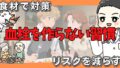

コメント