目次
体をサビから守っていく
私たちの体は、呼吸をしてエネルギーを生み出すたびに「活性酸素」という物質が生まれています。
活性酸素は体内のウイルスや細菌を退治するために必要な存在ですが、過剰になると細胞や血管を傷つけ、いわゆる「体がサビる」状態を引き起こし、これが酸化ストレスと呼ばれるもので、老化の大きな原因のひとつです。
酸化によって傷ついた細胞は機能を失いやすく、血管が硬くなる、肌にしわやたるみが増える、内臓の働きが低下するなど、さまざまな老化現象を招きます。
さらに進行すると、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞などの生活習慣病にもつながるのです。
まずは酸化のことを理解していき、今日から体を酸化させない生活習慣を作っていきましょう。

活性酸素はゼロにはできない
私たちの体は、酸素を使ってエネルギーをつくりながら活動しています。
呼吸で取り入れた酸素は細胞の中でエネルギー反応に利用されますが、その過程で必ず生じるのが「活性酸素」です。
体が動き続ける限り、生命活動の根幹であるエネルギー産生は止まらず、同時に活性酸素も生まれ続け、私たちは生きているだけで常に活性酸素にさらされているのです。
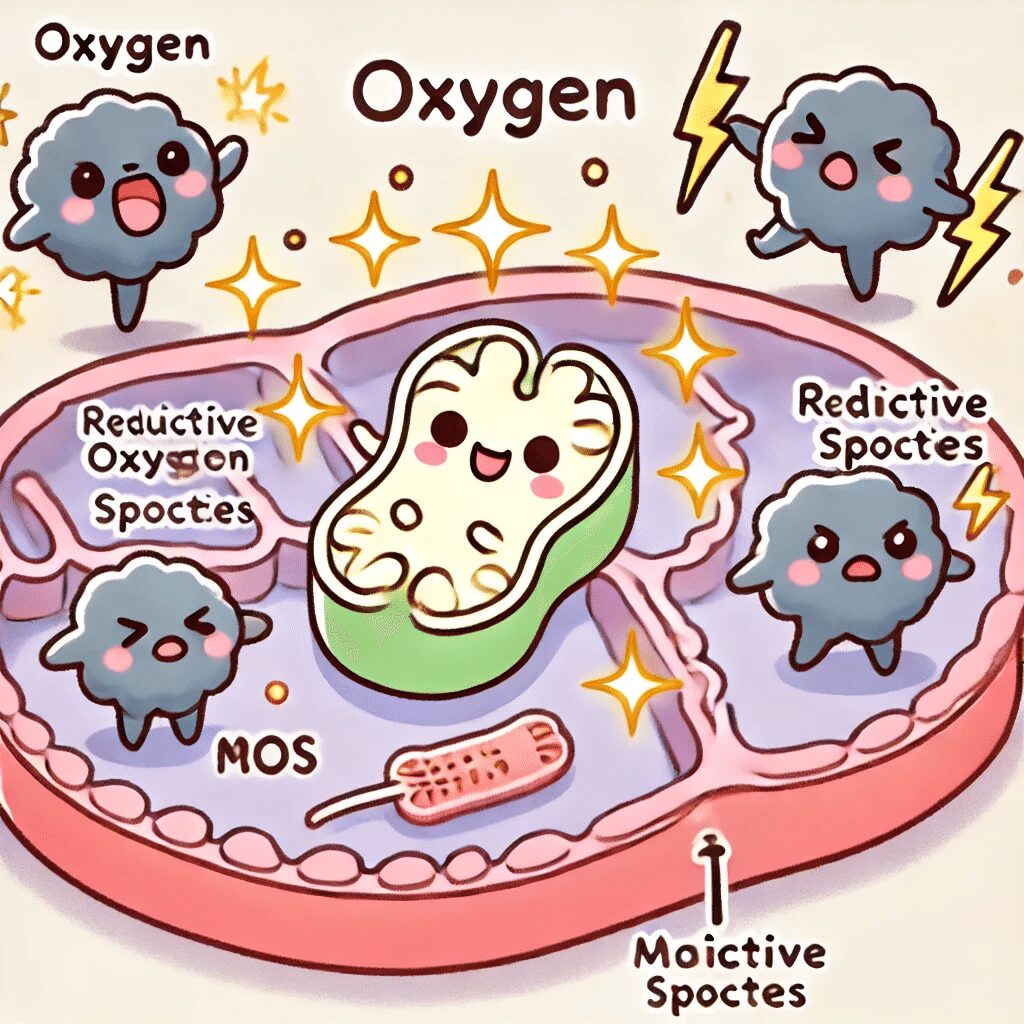
活性酸素にはいくつかの種類がありますが、そのひとつが「過酸化水素」と呼ばれるもので、過酸化水素は濃度が高まると細胞の膜や遺伝子を傷つけ、正常な機能を妨げてしまいます。
体内には、この活性酸素を無害化するための仕組みも備わっており、カタラーゼやグルタチオンペルオキシダーゼといった二つの主要な酵素が、過酸化水素を分解して水や酸素に変えています。
しかし、紫外線などの外的要因も活性酸素を増加させ、私たちが外に出て日光を浴びるだけでも、皮膚の細胞内で酸素が活性化され、活性酸素が発生するのです。
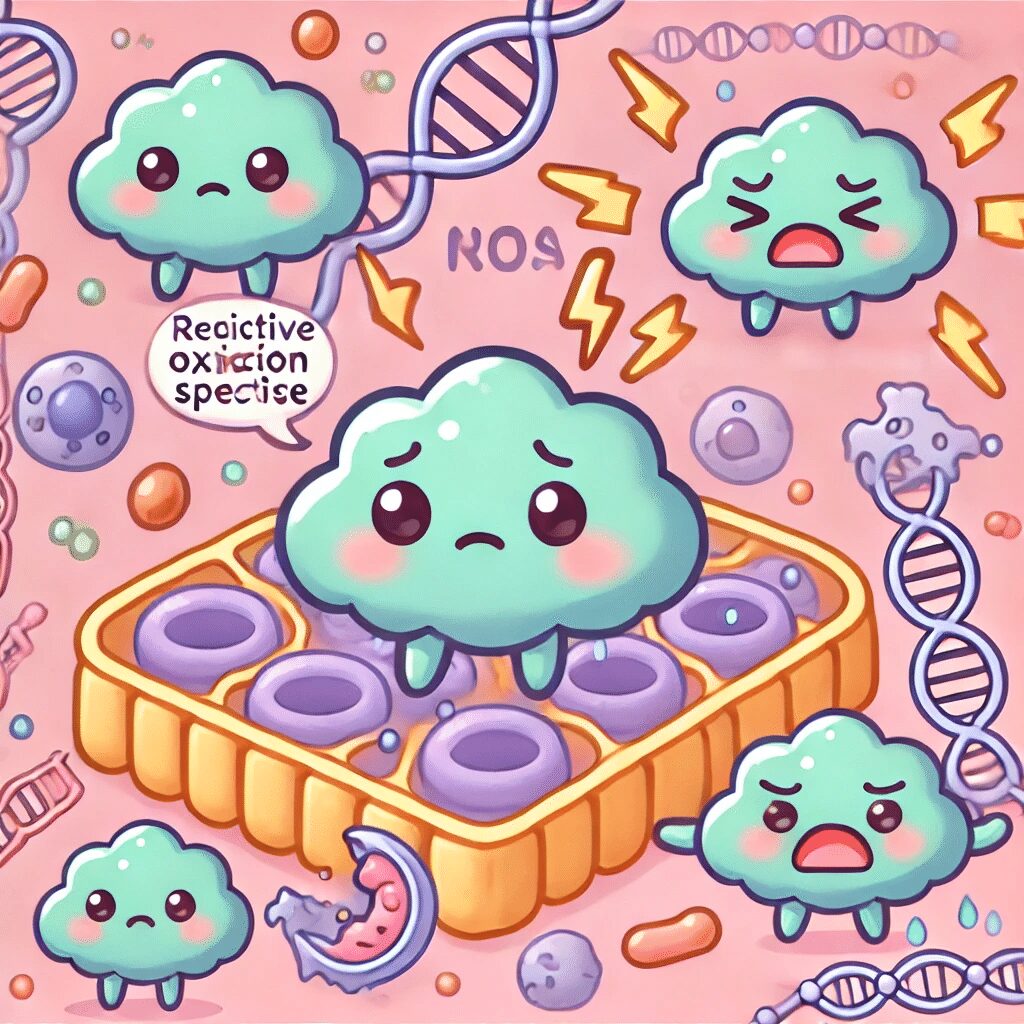
さらにストレスや過度な運動、喫煙、過剰な飲酒など、日常生活のさまざまな場面でも活性酸素は増えやすくなります。
 |
糖化は酸化も引き起こす
私たちの体内で進む糖化は、単にAGEsを生み出すだけではなく、AGEsそれ自体がさまざまな組織に悪影響を及ぼすだけでなく、病気の引き金となる活性酸素を発生させる性質を持っています。
糖化が進み、AGEsが増えるほど、体内では酸化反応も進行しやすくなり、老化が二重に加速してしまうのです。
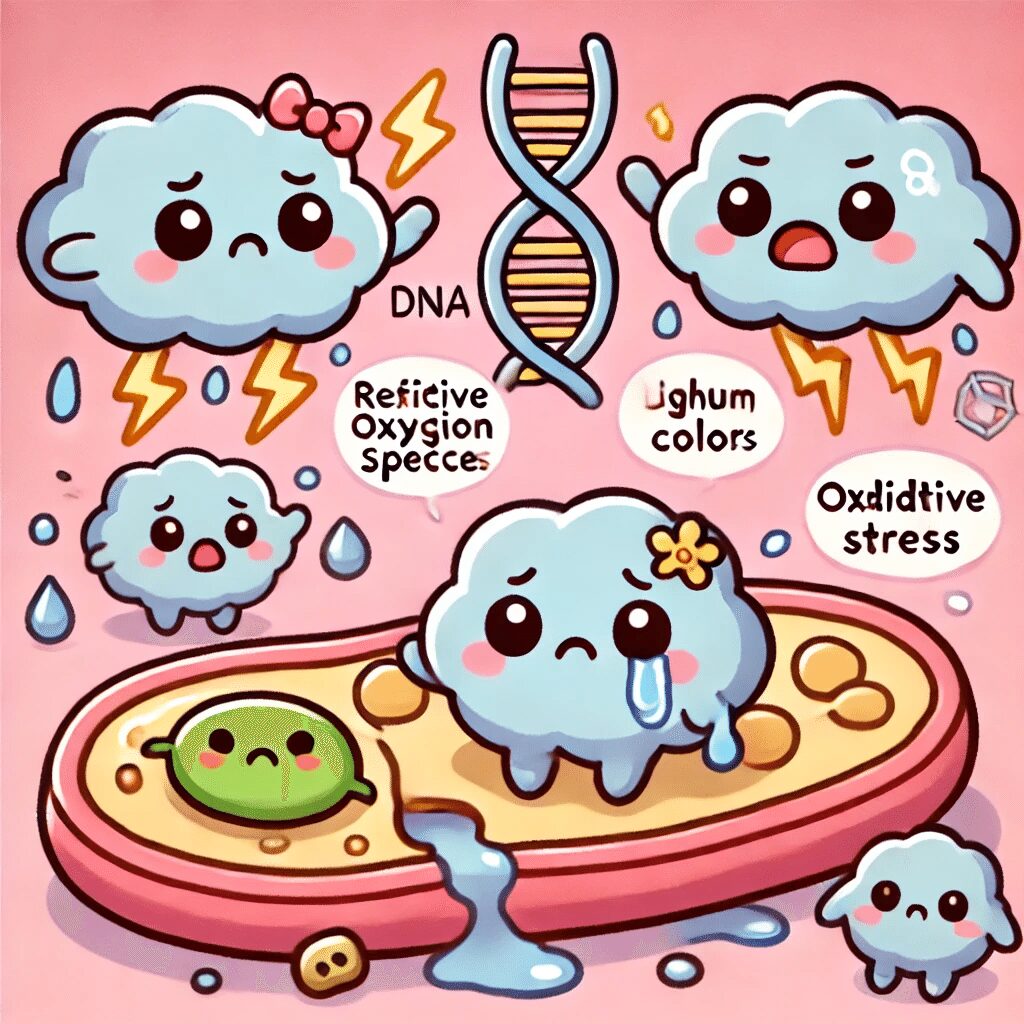
糖化と酸化は、まさにダブルパンチで体を傷めていき、糖化が細胞のタンパク質を劣化させ、そこから発生した活性酸素がさらに細胞や血管を攻撃
この悪循環が続くことで、しわやたるみ、血管の硬化、内臓の機能低下といった老化現象が一気に進んでしまうのです。
さらに、活性酸素を消去する働きを持つ体内の重要な酵素「SOD(スーパーオキシドディスムターゼ)」も、糖化の進行によってその機能が低下するといわれています。
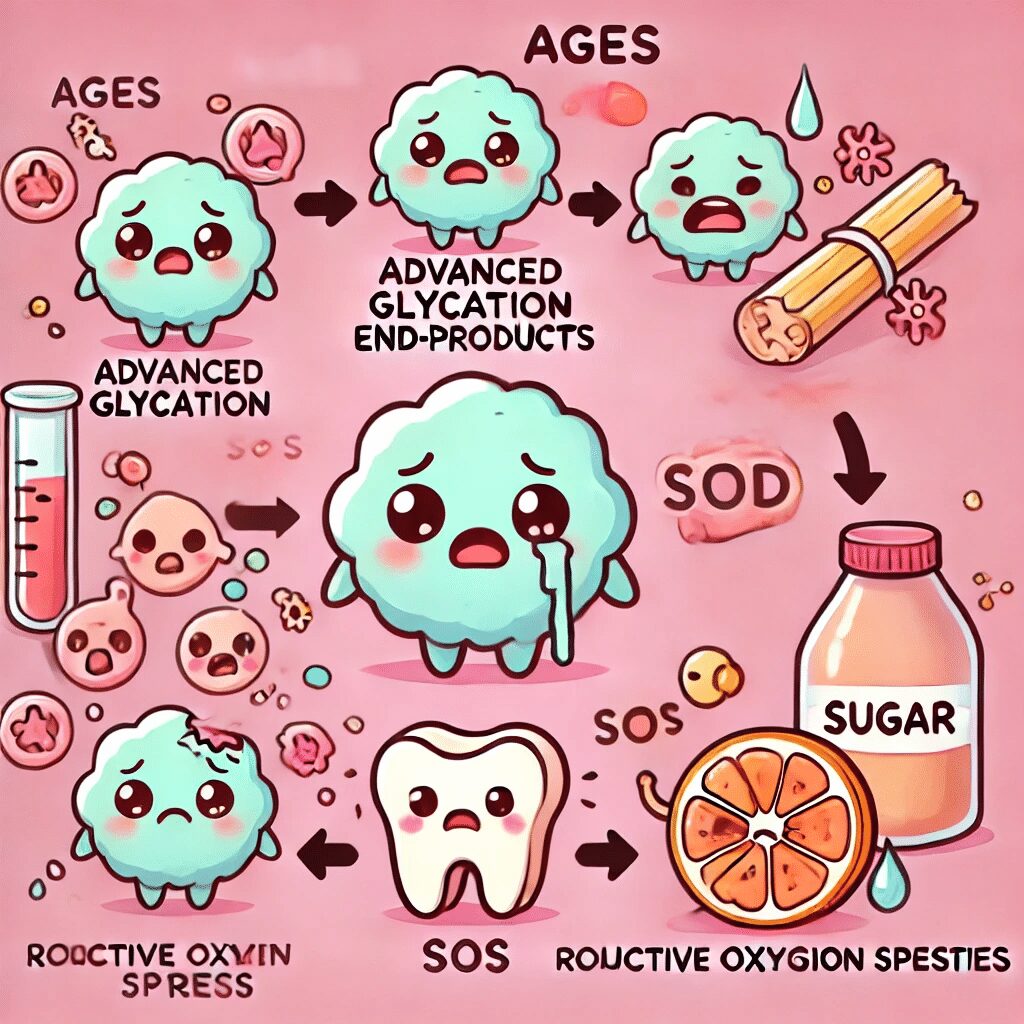
SODがうまく働かない状態では、増えすぎた活性酸素を処理できず、酸化ストレスはさらに強まります。
糖化を進めてしまう大きな要因の一つが、糖質の過剰摂取による血糖値スパイク。
血糖値が急上昇と急降下を繰り返すたびに、体内のビタミンCが消費され、活性酸素を除去する力が弱まります。
ビタミンCは抗酸化の要ですが、ブドウ糖と吸収経路を競合しており、血糖値が高いと体はビタミンCを十分に取り込めなくなり、その結果、活性酸素の処理が滞り、糖化と酸化が同時に進行するという悪循環に陥ってしまうのです。
このように、糖化は単独で老化を招くだけでなく、酸化を誘発し、老化のスピードをさらに早めます。
 |
普段の習慣が活性酸素を増加させる
私たちの体は、日常のさまざまな行動や環境によって活性酸素の量が変化します。
活性酸素は細菌を排除したり体を守る役割もありますが、過剰になると細胞を傷つけ、老化や病気を招く要因となるのですが、身近な習慣が、活性酸素を大量に発生させてしまうことがあるのです。
代表的なのが喫煙、タバコと聞くと「ニコチン」が注目されがちですが、実はニコチンだけが問題ではありません。
タバコを吸うだけで、煙の成分とともに体内で大量の活性酸素が発生し、血管や肺、肌に負担をかけ、続けていれば続けるほど、酸化ストレスは蓄積し、老化が進むことになります。

飲酒にも注意が必要となり、お酒を飲むと体内でアルコールは肝臓によって分解されますが、その過程で大量の活性酸素が生じます。
適度な飲酒なら問題は小さいものの、習慣的な多量飲酒は肝臓に大きな負担をかけ、老化を早める原因になるのです。
また、身近な薬も活性酸素を増やすきっかけになることがあり、頭痛薬や胃腸薬を長期間にわたって常用していると、肝臓での代謝負担が増し、結果的に活性酸素が多く生じる場合があるのです。
さらに、健康に良いとされる運動も、やりすぎれば逆効果に変わります。
適度な運動は血流改善や抗酸化酵素の増加を促しますが、過剰な負荷をかけ続けると筋肉や細胞にストレスがかかり、大量の活性酸素が発生してしまうので要注意。

そして見逃せないのがストレスで、過剰な精神的ストレスは自律神経を乱し、体内で活性酸素を急激に増加させることが知られています。
慢性的なストレスは、血管や内臓、肌にまで影響し、老化や病気を早める原因となるので、ストレスが溜まってしまう前に、ストレスの発散を行なっていきましょう。
コエンザイムQ10を味方に
酸化対策として近年注目されているのが「コエンザイムQ10」
コエンザイムQ10は、もともと私たちの体内に存在し、エネルギーを作るために欠かせない補酵素として働いています。
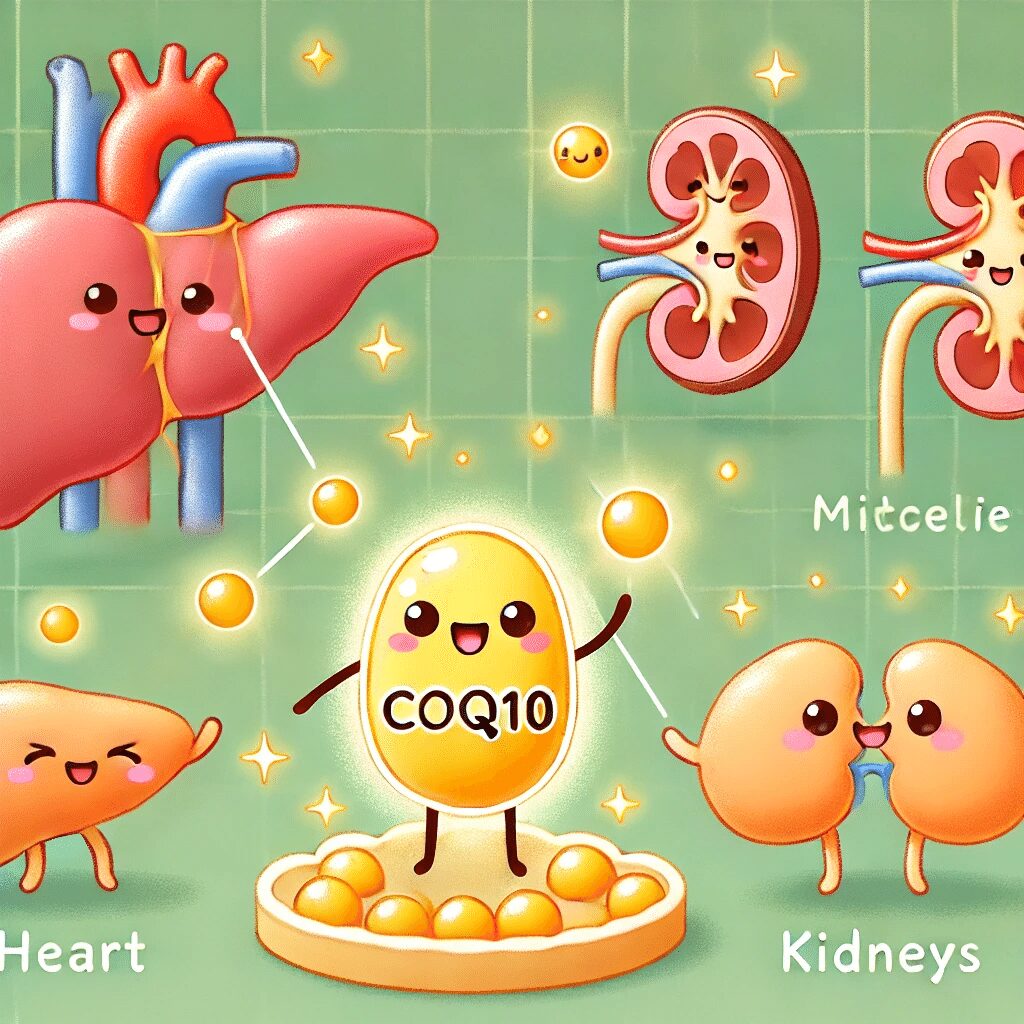
心臓や肝臓、腎臓といったエネルギーを多く必要とする臓器で豊富に存在し、細胞内のミトコンドリアでエネルギー産生を支える役割を担っているのです。
コエンザイムQ10の大きな特徴は、単なるエネルギー補酵素としてだけでなく「強力な抗酸化物質」としても働き、体内で発生した活性酸素を中和し、細胞膜や遺伝子が酸化によって傷つくのを防いでくれます。
活性酸素が増えすぎると、しわやたるみ、くすみなど肌の老化だけでなく、動脈硬化や心臓病、認知症といった生活習慣病のリスクが高まりますが、コエンザイムQ10で酸化ストレスを抑えることで、体の老化スピードを緩やかにする手助けをしてくれるのです。
ところが、体内のコエンザイムQ10は加齢とともに減少傾向になり、20代をピークに徐々に低下し、40代、50代になると大幅に不足しがちです。
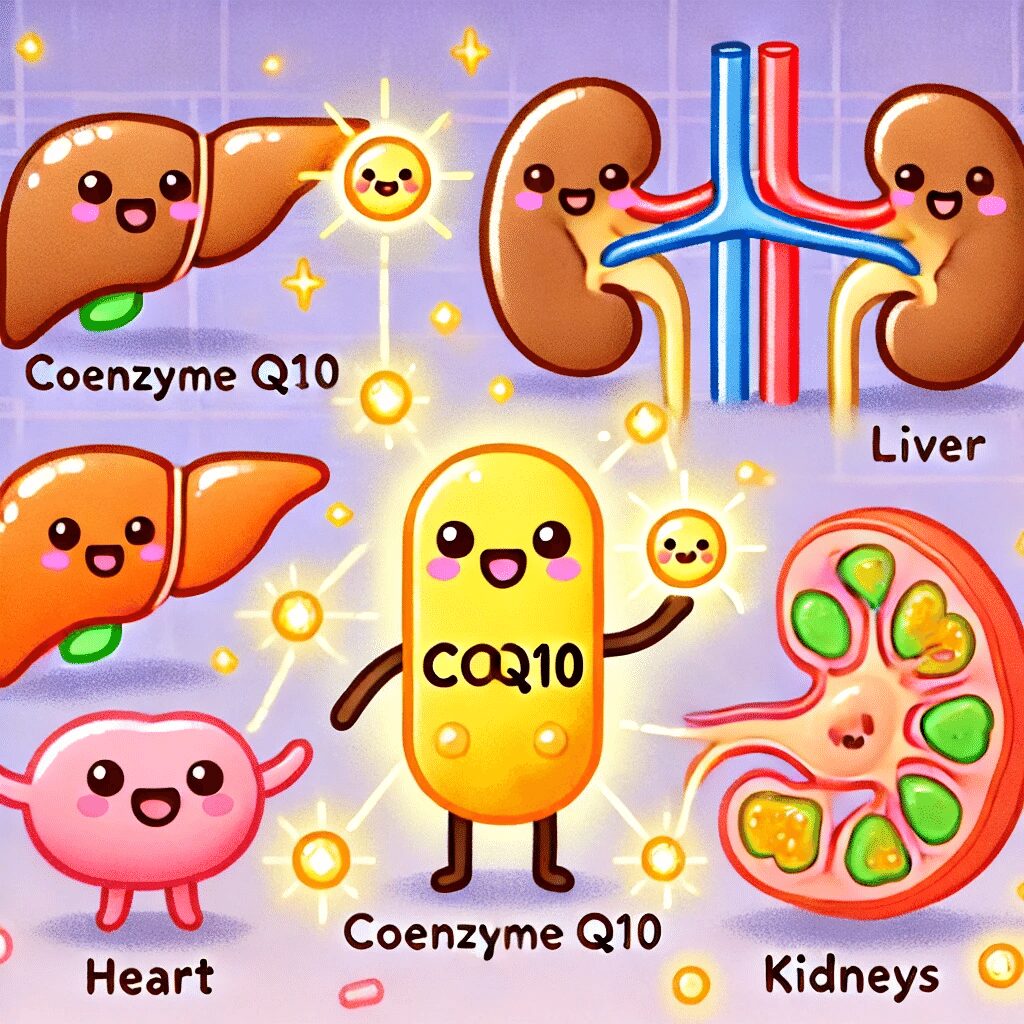
そのため、イワシやサバなどの青魚、豚肉や牛肉の赤身、ホウレンソウやブロッコリーといった緑黄色野菜にはコエンザイムQ10が含まれ、積極的にとることが推奨されています。
コエンザイムQ10は脂溶性なので、油を使った調理で摂取すると吸収率が上がるので、オリーブオイルやごま油など良質な油と一緒に調理していきましょう。
食べて抗酸化力を高める
私たちの体を酸化ストレスから守るためには、日々の食事で「抗酸化力」を高めることがとても重要です。
抗酸化力は特別なサプリメントに頼らずとも、普段の食べ物から自然に補うことができ、毎日の食卓で選ぶものを少し意識するだけで、体の内側から老化を防ぐ力を強くすることができるのです。

心がけたいのは、新鮮で旬の食材を選んでいき、旬の野菜や果物は栄養価が高く、抗酸化成分が豊富に含まれています。
色の濃い緑黄色野菜は抗酸化食品の代表格、カロテノイドをはじめとする抗酸化成分が豊富で、トマト、ピーマン、芽キャベツ、ブロッコリーなど、これらの野菜は細胞を守り、酸化によるダメージを和らげる力を持っています。
果物も抗酸化食品として優れ、ブルーベリーやキウイ、イチゴなどにはビタミンCやポリフェノールが豊富に含まれ、体内で発生した活性酸素を抑える働きが期待できます。
色鮮やかな果物を毎日の食事や間食に取り入れることで、自然と抗酸化力を底上げすることができるでしょう。

抗酸化力を高めるには「ビタミンエース(ACE)」と呼ばれるビタミン群を意識して摂ることがポイントです。
ビタミンA、C、Eは互いに協力し合って酸化ダメージから体を守り、肌や血管、内臓を若々しく保ち、緑黄色野菜やナッツ類、柑橘類、赤やオレンジの果物にこれらのビタミンが豊富です。
普段から重要とされる鉄分や亜鉛といったミネラルも、抗酸化力を支えるためには欠かせませず、これらのミネラルは酵素の働きを助け、体内で抗酸化成分を活かす土台となるので、赤身の肉や魚、貝類、豆類などからバランスよく摂取するよう心がけましょう。
酸化を加速してしまう揚げ物
揚げ物は香ばしく食欲をそそる料理ですが、体の酸化や糖化を進めやすい調理法で、高温で食材を加熱すると、タンパク質と糖が結びつきやすくなり、AGEsを多く発生します。
肉や魚などタンパク質を多く含む食材を高温で揚げると、AGEsの生成量がぐっと増えるため、揚げ物を頻繁に食べる人ほど体の中で糖化と酸化が進みやすくなります。
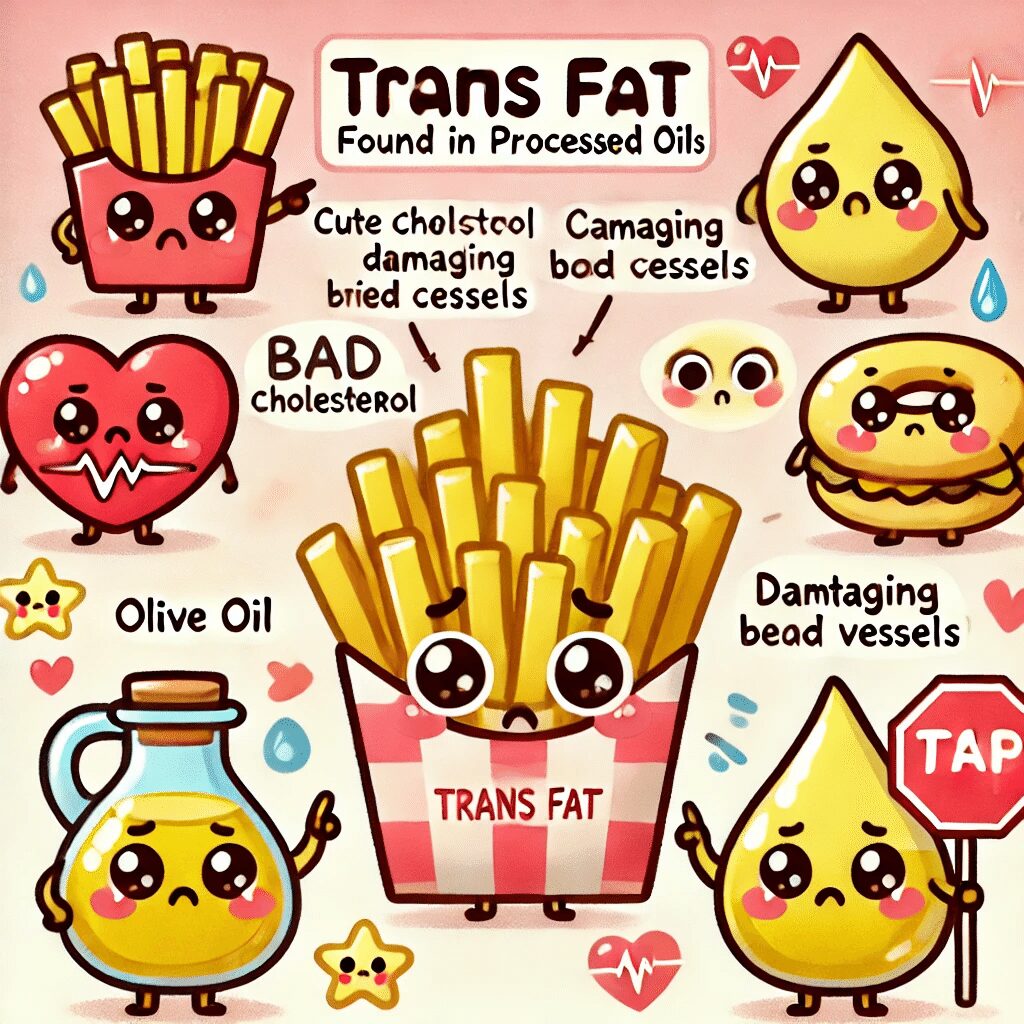
また、揚げ物で使われる油の種類にも注意が必要になり、市販の加工食品や外食で使われがちな「トランス脂肪酸」を多く含む油は、体内で酸化を促進させやすいことが知られています。
トランス脂肪酸は血中の悪玉コレステロールを増やし、動脈硬化を進め、心臓病や脳卒中のリスクを高める要因にもなるので、揚げ物を選ぶ際には、どのような油が使われているかにも意識を向けたいところです。
さらに、家庭でも外食でも、同じ油を何度も繰り返し使うことは避けなければなりません。
油は加熱するたびに酸化が進み、劣化した油には過酸化脂質が増加、これを体に取り込むと、活性酸素の発生が増え、血管や細胞を傷つけるリスクが高まります。
揚げ物を作る場合は、新しい油を使い、調理後は何度も使い回さず適切に処分することが望ましいでしょう。
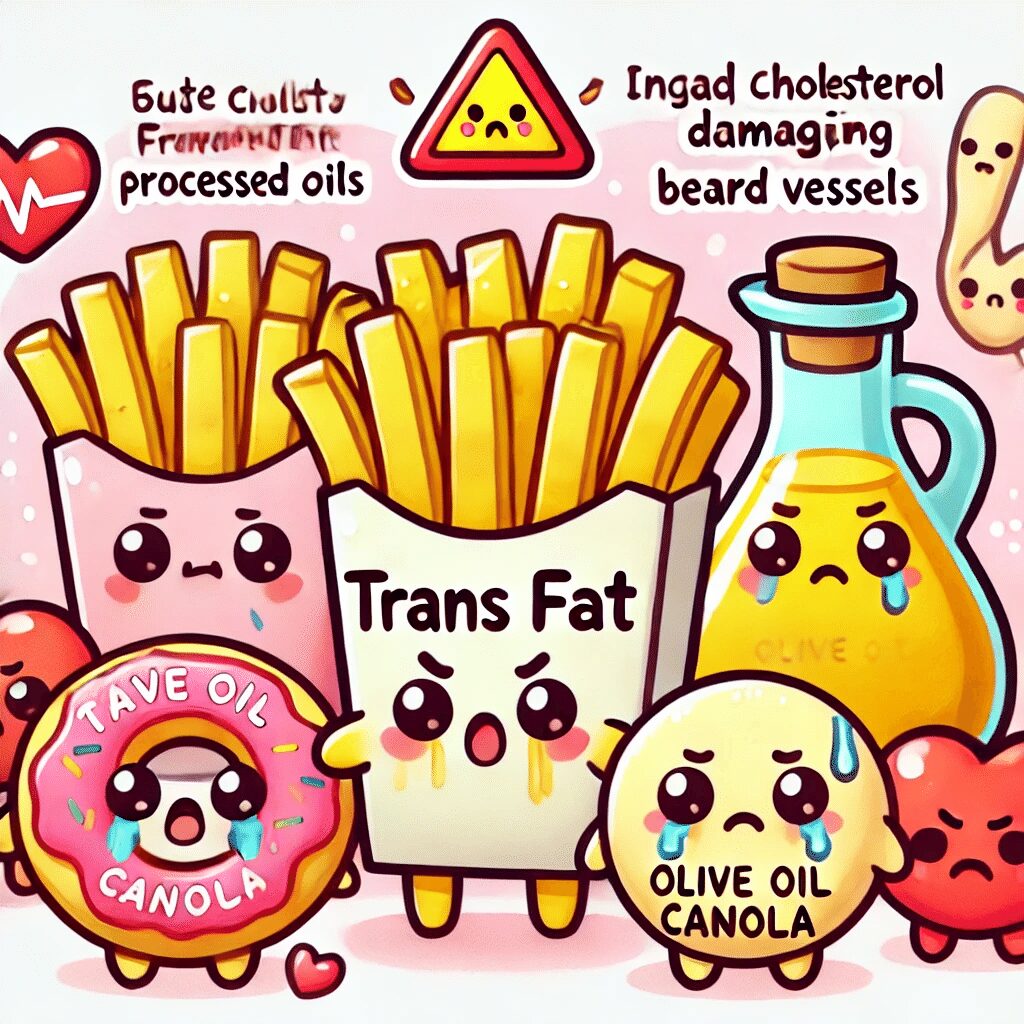
もちろん、揚げ物を完全にやめる必要はありませんが、頻度を控え、揚げる温度や時間、使う油に気を配ることで、体への負担を減らすことができます。
オリーブオイルや米油など酸化に強い油を使い、できるだけ新鮮なものを選ぶことも効果を発揮し、こうした小さな工夫が、体を酸化ストレスから守り、健康で若々しい体を維持するための大切な習慣となるのです。
まとめ
体を「サビ」から守るために、酸化ストレスの正体とその対策が解説されています。
呼吸や代謝の過程で必ず生じる活性酸素は、必要不可欠である一方、増えすぎると細胞や血管を傷つけ、老化や生活習慣病を引き起こします。
糖化も酸化を促進し、しわ・たるみ・動脈硬化などの悪循環を生む要因です。
さらに喫煙、多量飲酒、薬の常用、過度な運動やストレスも酸化を加速させる習慣として挙げられます。
一方で、コエンザイムQ10やビタミンACE、ポリフェノール、ミネラルを含む食材は抗酸化力を高め、体を守ります。
揚げ物や劣化した油は酸化を進めるため注意が必要ですが、油の種類や調理法を工夫することでリスクを減らすことができます。
日々の小さな選択や工夫が、老化を遅らせ、健康を守る大切なカギになるのです。

最後まで見ていただきありがとうございました。
↓終活で分からない事や迷子になったら↓
このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています
LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV
インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/
アマゾンで本を出品しています

 |
- 【無意識に老化を進める習慣】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【食で体を保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【心を保つ習慣を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【習慣で革命を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【生涯健康体】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

28-3
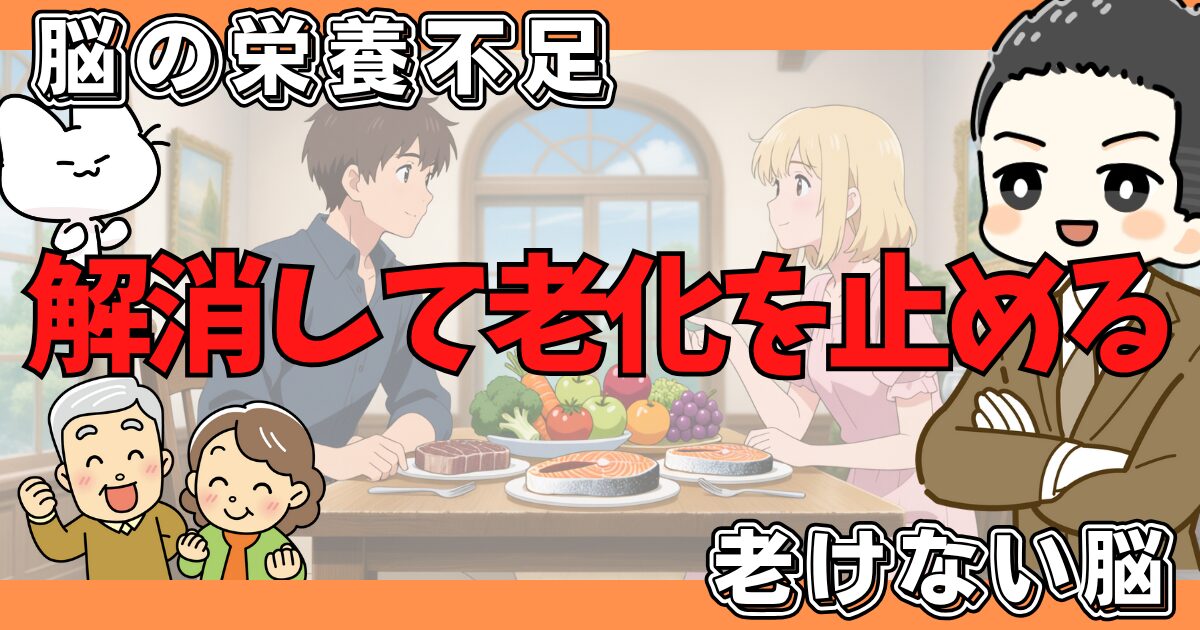






コメント