目次
はじめに
「眠っているのに疲れが取れない」「寝てもスッキリしない」そんな声をよく耳にします。
実は、眠りの“長さ”よりも“質”こそが、心と体の回復を左右する鍵になり、睡眠は、単なる休息の時間ではなく、脳や内臓、ホルモンの働きを整え、翌日のエネルギーを生み出す大切なメンテナンスの時間。
けれど、現代人の生活は夜型化が進み、スマホやストレス、運動不足などが眠りの質を低下させています。

今回は「朝の過ごし方」「寝室環境」「お風呂」「仮眠」など、すぐに実践できる“快眠習慣”を紹介します。
眠りを変えることは、人生を変えること、今日からできる小さな一歩で、心も体も軽くなる「本当に休まる眠り」を手に入れていきましょう。

今日から実践する快眠習慣
睡眠はただただ長く眠る、寝溜めをするといったことよりも、適切な量と高い質を確保して、規則正しい睡眠をとることが重要です。
睡眠をよくするためにも環境が大切になり、生活習慣を見直していき、睡眠をとる寝室の改善も快眠に影響します。

いきなり大きく生活習慣を変えずに、自分にできることを実践していき、快適な睡眠をとっていきましょう。
睡眠は朝の過ごし方で決まる
人の体には「体内時計」が備わっており、約24時間のリズムで体の機能が動いています。
このリズムを司るのが、脳の視交叉上核という部分にある中枢時計で、朝に太陽の光を浴びることでこの体内時計がリセットされ、「今日も一日が始まった」と体に伝えられます。
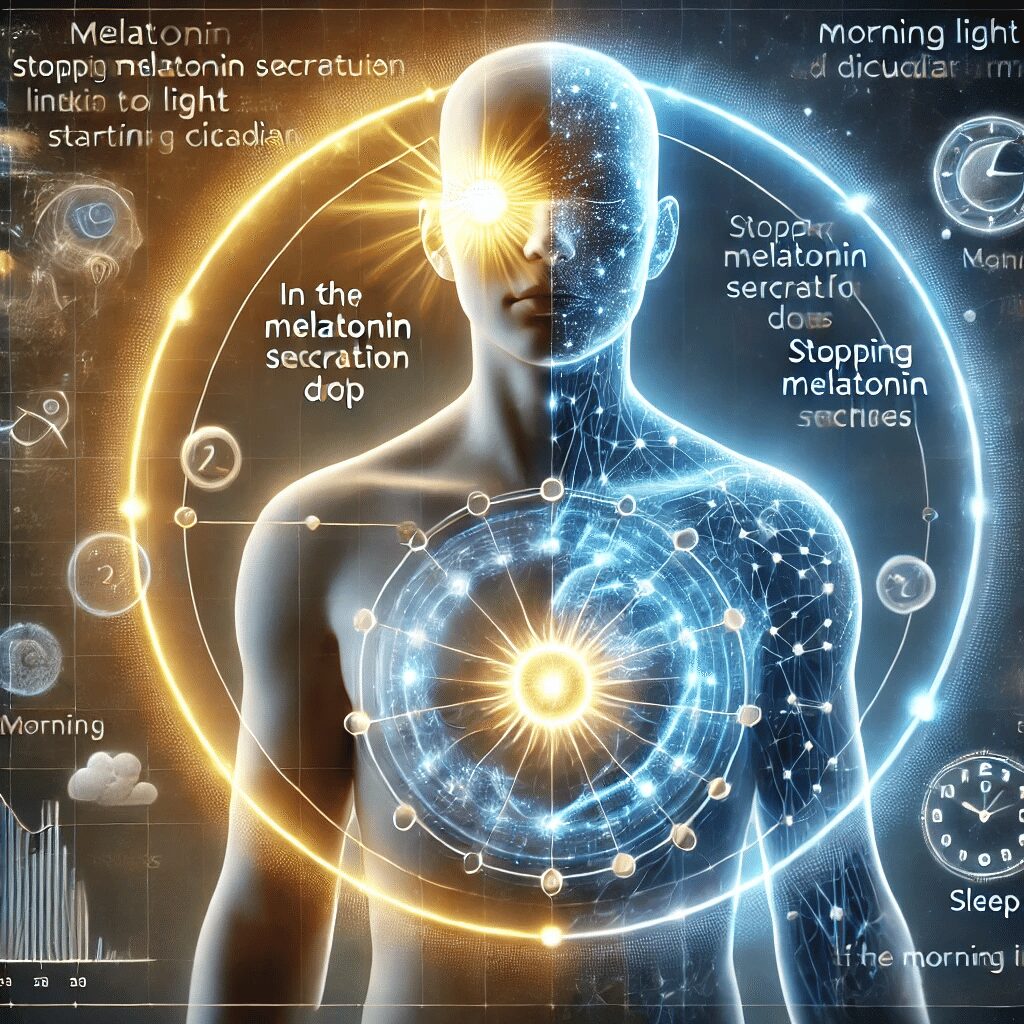
そしてこのリセットから約15〜16時間後、自然と眠気が訪れる仕組みになっているのです。
朝に光を浴びることで、夜の眠りのスイッチも同時にセットされるのですが、朝の光が弱かったり、起きてすぐにカーテンを開けなかったりすると、体内時計がずれてしまい、夜の入眠にも影響が出てしまいます。
これが、寝つきが悪い、眠りが浅い、早朝に目が覚めるといった不調の原因になりやすいのです。
また、朝の活動量もその日の眠りに大きく影響し、朝食をしっかりとる、軽いストレッチや散歩などで体を動かすことで、交感神経が優位になり、体と脳が目覚めていきます。
日中にしっかり活動することで、夜になれば自然と副交感神経が優位になり、体はリラックスモード、この自律神経の切り替えがスムーズに行われることが、深い眠りに入るための土台となるのです。
朝にしっかり目が覚めることで、「メラトニン」という睡眠ホルモンのリズムも整います。
メラトニンは夜になると分泌が増えて眠気を誘いますが、朝に光を浴びることでその分泌が一度止まり、体内時計がスタートします。
そしておよそ14〜16時間後、再びメラトニンが分泌され始めるのですが、朝の時間がズレれば、メラトニンのリズムもズレてしまうため、夜の眠りの質も下がってしまいます。
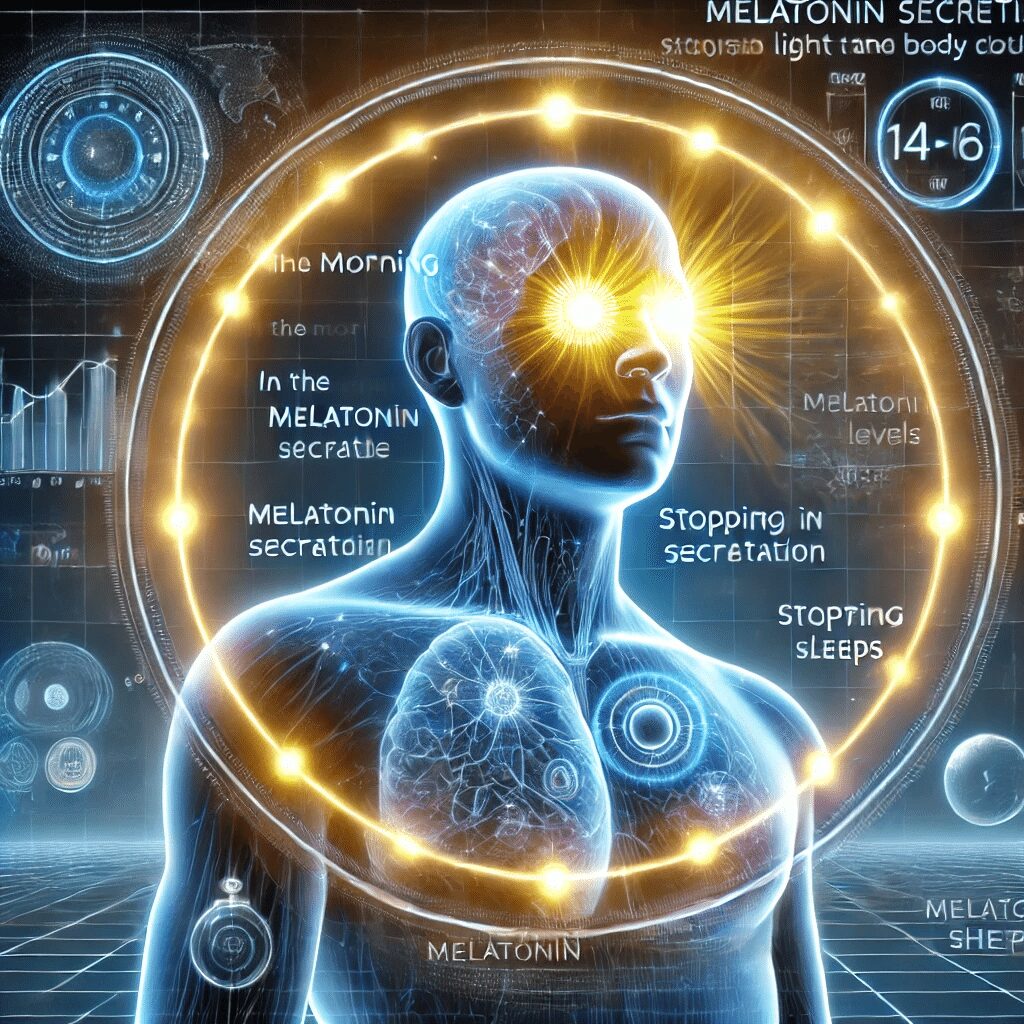
忙しい日々の中で、夜の過ごし方にばかり気を取られてしまいがちですが、実は「朝の一時間」をどう使うかが、その日の眠りを左右しています。
朝起きたらカーテンを開けて太陽の光を浴び、少し体を動かす、温かい飲み物で体温を上げる、こうした行動が夜の快眠につながっていくのです。
一日のスタートを整えることが、一日の終わりを良いものにしてくれるので、「ぐっすり眠りたい」と思ったら、まずは朝の習慣を見直してみましょう。
短い二度寝も効果的に
朝、いったん目覚めた後にもう一度まどろむ「二度寝」、多くの人にとっては「だらしない習慣」「時間の無駄」といったネガティブな印象を持たれがちですが、実はこの二度寝にも、うまく取り入れることで心身にプラスの効果が期待できる場面があります。
ポイントは二度寝の「時間」で、長く寝てしまうと体内時計が乱れたり、かえって寝起きが悪くなったりしますが、朝の短時間、20分以内の二度寝であれば、ストレス軽減や心の安定につながる効果が報告されています。
この仕組みに関係しているのが、「コルチゾール」というホルモンです。

コルチゾールはストレスに対抗するために働くホルモンで、起床の1〜2時間前から分泌が急激に高まり、これは、私たちの体が日中のストレスに備える“ウォーミングアップ”のようなものです。
朝にかけてコルチゾールが増えることで、私たちは自然と目覚め、1日の活動に向けて準備を整えているのです。
このタイミングでいったん目覚め、そこからほんの少しだけ再びまどろむことで、体と脳がじっくりと覚醒し、気持ちも前向きになりやすくなります。
つまり、無理やり布団から飛び起きるよりも、少しゆとりを持って短い二度寝を取り入れることで、スッキリとした目覚めが得られるというわけです。

ただし、注意すべきは「二度寝の時間が長くなりすぎないこと」、20分を超えてしまうと、再び深い眠りに入ってしまい、脳が中途半端な状態で起こされることになります。
これが「寝すぎて逆にだるい」「一日中ぼーっとしてしまう」といった状態の原因で、効果的な二度寝を行うには、時間をあらかじめ決めて、タイマーをセットするのがおすすめです。
睡眠はいい環境作りから
質の良い睡眠を得るためには、生活習慣や就寝前の行動だけでなく、「睡眠環境」を整えることがとても大切です。
眠る部屋の温度や明るさ、音、香りなどの要素は、睡眠の深さやリズムに大きな影響を及ぼし、心地よい眠りを導くためには、五感に働きかける“快適な環境作り”から始めることが基本です。

まず、睡眠に適した室温・湿度の調整が欠かせません。理想的な室温は、夏場なら25〜28度、冬場なら15〜18度が目安とされています。
また、湿度は40〜60%が最適とされており、乾燥や蒸し暑さがあると、呼吸や皮膚に負担がかかって眠りが浅くなり、エアコンや加湿器・除湿機をうまく活用して、四季に応じた空気環境を整えることが重要です。
音についても、睡眠の妨げになり、騒がしい音や突発的な物音は、眠りを中断させたり、浅くしたりします。
できるだけ静かな環境を心がけることが大切ですが、完全な無音では逆に不安感を抱く人もいますので、おすすめなのが「1/f(エフぶんのいち)ゆらぎ」と呼ばれる自然のリズムをもった音です。
たとえば、小川のせせらぎや雨音、波の音などが代表的で、こうした音は心を落ち着け、自律神経を整え、眠気を誘う効果があるとされています。
照明にも気を配り、夜間は部屋を暗くし、暗さは睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を促し、自然な眠りを導きます。
明るい照明やスマートフォン、テレビなどの強い光は、脳を刺激してしまい、入眠の妨げになっていき、就寝前は間接照明や暖色系の明かりに切り替え、目と脳を休める時間にすることが大切です。
また、寝具の環境も重要で、布団の中が熱くなりすぎると、深部体温がうまく下がらず、眠りが浅くなることがあります。
冬場は布団の中と外気の温度差が大きくなりがちですが、この差が大きすぎると血管に負担をかけるので、湯たんぽや電気毛布を使う際も、適温に調節し、寝入りばなに体が温まり、その後は自然に放熱されるよう工夫しましょう。

さらに、「香り」も睡眠環境において見逃せない要素になり、アロマの香りは自律神経に働きかけ、心身をリラックスさせる効果をもたらしてくれ、ラベンダー、カモミール、ベルガモットなどの香りは、入眠をサポートするとして多くの研究でも支持されています。
アロマディフューザーを使ったり、枕元にアロマオイルを染み込ませた布を置くなどして、香りの力を上手に活用してみましょう。
深い睡眠には適度な疲れも
質の良い睡眠「深い眠り」を得るためには、昼間の過ごし方も関わり、注目したいのが「適度な疲れ」、つまり日中に体を動かすことによる身体と脳の自然な疲労です。
私たちの睡眠は、ただ横になるだけでは深くなりません、脳や体に「休息の必要性」があるときにこそ、ぐっすりとした眠りに入ることができるのです。
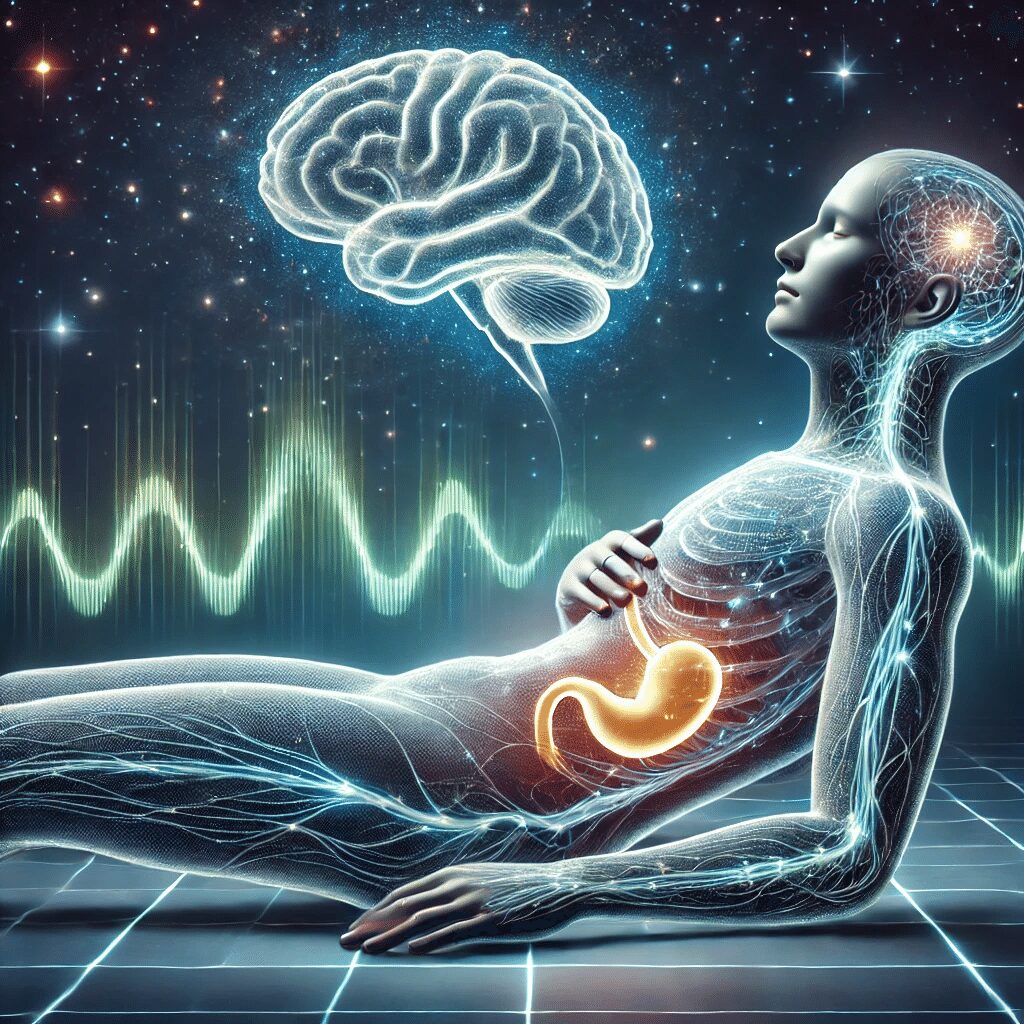
昼間に活動量が少なく、座りっぱなしの生活をしていると、体も脳もそこまで休息を求めておらず、浅い眠りで終わってしまうことがあります。
そのため、日中に軽く体を動かすだけでも、脳と体に適度な疲労が生まれ、それを回復させようと深い睡眠が得られるのです。
ウォーキングのような軽い有酸素運動は、誰にでも取り組みやすく効果も高い方法のひとつ、目安としては1日あたり5000〜1万歩を目標に、無理のない範囲で歩くことを心がけましょう。
運動といっても、激しいトレーニングをする必要なく、大切なのは、毎日こつこつと継続することです。
また、運動後には軽くストレッチを行うことで、筋肉の緊張をほぐし、血流を促進させ、リラックス効果を高めることができます。
さらに、日常生活の中で「腹式呼吸」を意識するだけでも、自律神経のバランスを整える効果があり、腹式呼吸は副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせるため、入眠時にもスムーズに深い眠りへと導いてくれます。
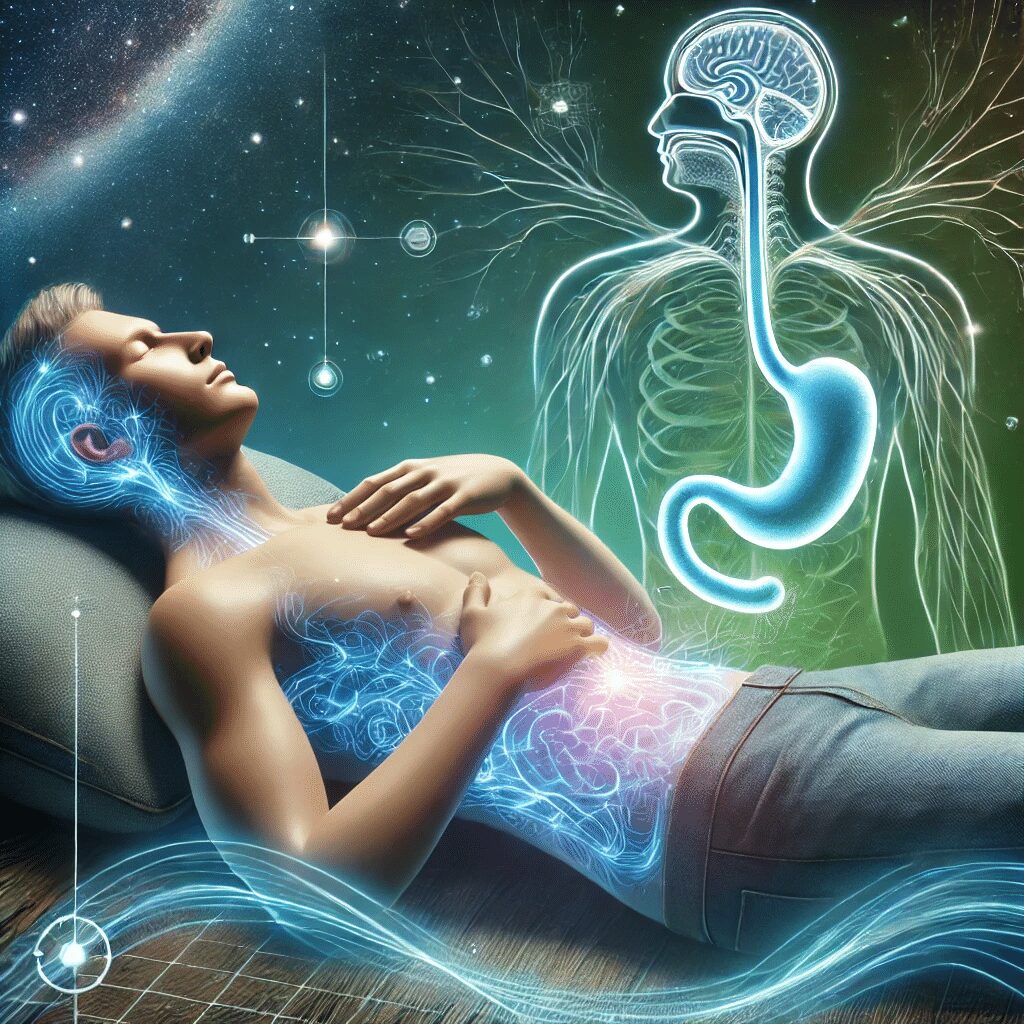
注意すべき点はやりすぎないこと、急に張り切って長時間歩いたり、無理な運動をしたりすると、筋肉痛や関節の痛み、場合によってはけがにつながってしまい、逆に睡眠を妨げる原因にもなりかねません。
まずは無理のない運動量から始め、徐々に体を慣らしていくことが大切です。
お風呂も睡眠に深く関わる
毎日の眠りの質を高めたいと思ったとき、見落とされがちなのがお風呂になり、入浴はただ体を清潔にするだけでなく、睡眠の質にも深く関わる重要な習慣なのです。
その鍵となるのが、「深部体温」と呼ばれる体の内側の温度のことで、人の体は、夜になるとこの深部体温を自然と下げていくことで、眠りに入りやすい状態を作っています。

逆に、深部体温が高いままだと、脳や内臓が活性化したままとなり、なかなか眠りにつけなかったり、眠りが浅くなってしまうのです。
そこで効果的なのが「入浴」、お風呂に入ると一時的に体温が上がりますが、その後、体は深部体温を下げようとし、皮膚から熱を放出し自然と深部体温をさげ、眠気を誘いやすくなるのです。
ポイントは「タイミング」と「温度」、入浴するのは寝る1〜2時間前がベストとされ、夜10時に就寝するなら、夜8時〜9時ごろに入浴を済ませておくのが理想となり、そうすると、就寝時には体がちょうどよく冷えて、眠りに入りやすくなります。
また、お湯の温度にも注意が必要で、熱すぎるお湯は交感神経を刺激し、かえって目が冴えてしまうことがあります。
理想は38〜40度程度のぬるめのお湯にゆっくりと浸かり、10〜15分ほどの半身浴でも効果的で、体に無理な負担をかけずにリラックスできるのです。

さらに、入浴には精神的なリラックス効果もあり、ぬるめのお湯にゆったりと浸かることで副交感神経が優位になり、心が落ち着き、ストレスも軽減されます。
照明を少し落としてアロマオイルを使ったり、好きな音楽を流したりすると、より心地よい入浴時間となり、睡眠へのスムーズな導入につながっていくのです。
 |
悪習慣を断ち切ることも重要
質の良い睡眠を手に入れるために、生活習慣の見直しは欠かせません。
寝室の環境を整えたり、規則正しいリズムを意識することも大切ですが、それと同じくらい重要なのが、「睡眠を妨げる悪習慣」を見直していき、知らず知らずのうちに続けている行動が、深い眠りを妨げているかもしれません。
まず代表的なのが「タバコ」、タバコに含まれるニコチンは、交感神経を刺激する興奮作用があり、睡眠の妨げになります。
就寝前の喫煙は脳を覚醒させてしまい、眠りが浅くなる、寝つきが悪くなるなどの影響が出やすく、睡眠の質を本気で高めたいのであれば、禁煙に取り組むことが重要になるのです。
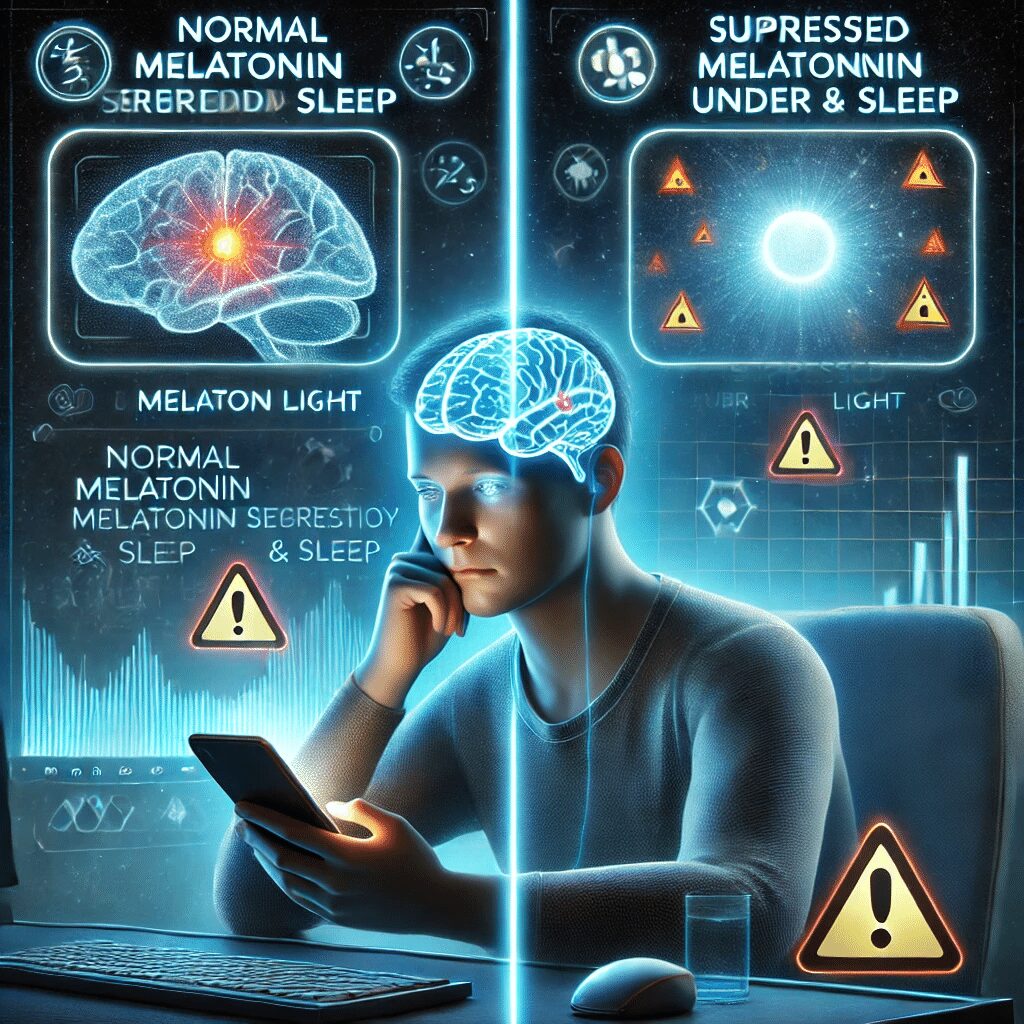
次に注意したいのが「寝る前のスマートフォンやパソコンの使用」です。
これらのデバイスから発せられるブルーライトは、脳に「今は昼間だ」と錯覚させ、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を妨げてしまいます。
メラトニンが分泌されにくくなると、自然な眠気が訪れず、結果として入眠までに時間がかかったり、夜中に目が覚めやすくなってしまうので、眠る1時間前には画面を見るのをやめ、目と脳を休ませていくのが望ましいです。
また、「お酒」も注意が必要となり、寝酒をすると眠りやすくなると感じる方もいるかもしれませんが、実はこれは大きな誤解になります。
確かにアルコールは入眠を早める傾向がありますが、その反動として深い眠りが減り、夜中に目覚めやすくなるというデメリットがあります。
アルコールが分解される過程で交感神経が刺激され、心拍数が上がり、結果的に睡眠の質が低下してしまうのです。
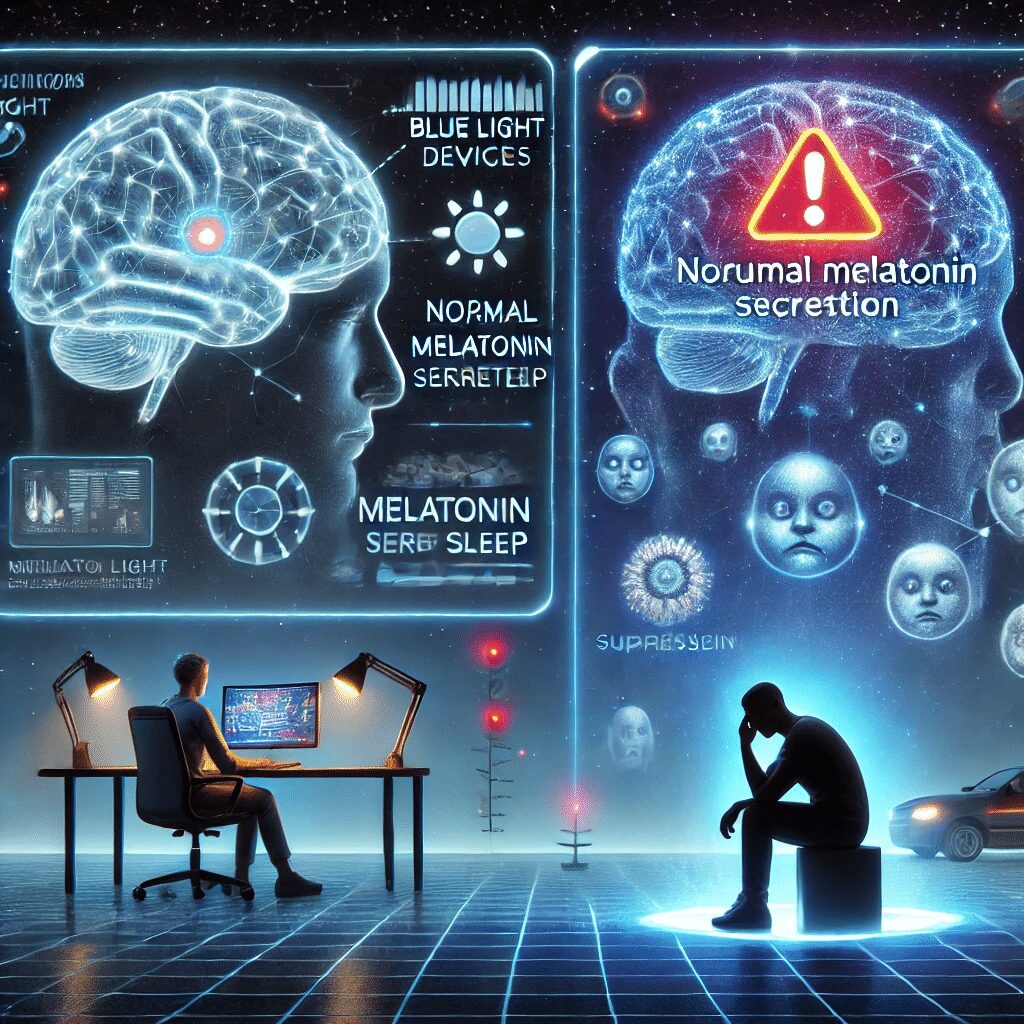
「カフェイン」も睡眠に影響を及ぼす代表的な成分で、コーヒーや紅茶、緑茶、さらにはエナジードリンクなどに多く含まれるカフェインは、摂取後4〜6時間は体内に作用し、脳を興奮させる働きがあります。
就寝前はもちろん、午後の遅い時間帯の摂取にも注意が必要になり、カフェインに敏感な人は、午後2時以降は控えるようにしていきましょう。
さらに、「就寝前の激しい運動」も避けたい習慣のひとつで、運動は睡眠にとって基本的には良い影響を与えますが、タイミングを誤ると逆効果になります。
寝る直前の激しい運動は、体温や心拍数を上げ、交感神経を刺激するため、眠りに入りにくくなるので、運動は夕方から夜の早い時間に行い、就寝の1〜2時間前までには終えるのが理想になっていきます。
眠れないなら無理をしない
眠れない夜、布団の中で「早く寝なきゃ」と焦ってしまった経験は誰にでもあり、眠れないまま無理に寝ようとすることは、逆効果に働き、眠ろうとするプレッシャーや焦りがストレスとなり、さらに眠気を遠ざけてしまう原因になります。
人は本来、眠くなると自然に眠りにつく力を持っているので、無理に目を閉じて寝ようとするのではなく、いったん布団を離れる勇気も大切です。

30分ほどたっても眠れないようなら、軽くストレッチをしたり、温かいお茶を飲んだり、静かな音楽を聴くなど、心身をリラックスさせる行動をとってみることで、自然に眠気が訪れたときに再び寝床に戻ると、スムーズに眠れることが多いのです。
また、6時間程度眠った後に目が覚めてしまった場合でも、無理にもう一度眠ろうとせず、スッと起きて朝の準備に入るのもひとつの方法です。
実際、自分にとって必要な睡眠時間は人によって異なり、長さよりも「満足感」が重要だと言われています。
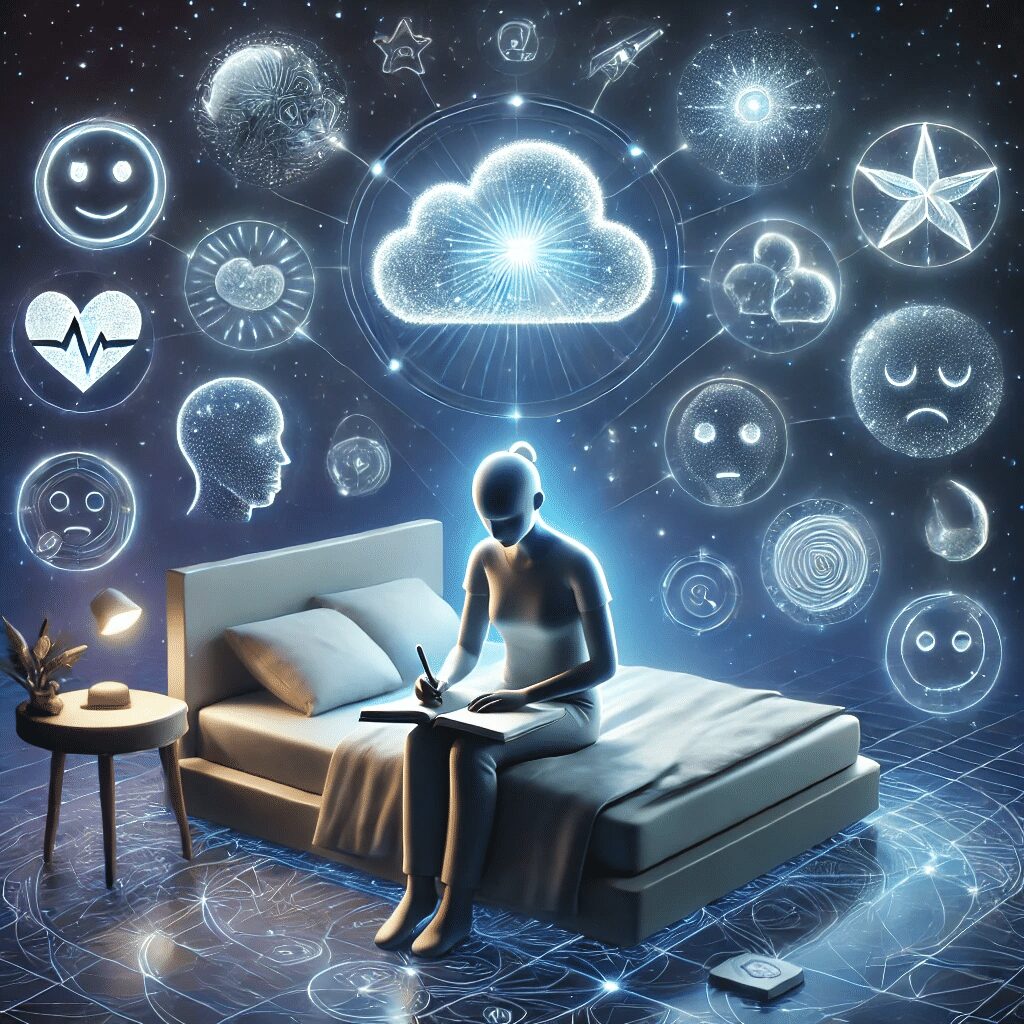
さらに、寝る前に感じた不安や怒り、心配ごとはなるべく解消しておくことも良い睡眠へのカギとなり、悩みごとを寝床に持ち込まないよう、ノートに書き出したり、軽く人と話したりして、心を整理しておく習慣を身につけるとよいでしょう。
仮眠を効率よくとろう
実は仮眠は、うまく取り入れることで、午後の集中力や作業効率を大きく向上させてくれる、非常に効果的な健康習慣なのです。
人間の体には、1日24時間の中で自然と眠気が訪れる時間帯があり、その代表的な時間が午後2時〜4時頃、昼食後のこの時間帯に強い眠気に襲われるのは、食事の影響だけでなく、体内時計(サーカディアンリズム)による自然な反応でもあるのです。
この眠気を我慢して作業を続けると、集中力が低下し、効率が落ちてしまうだけでなく、ストレスやイライラの原因にもなります。
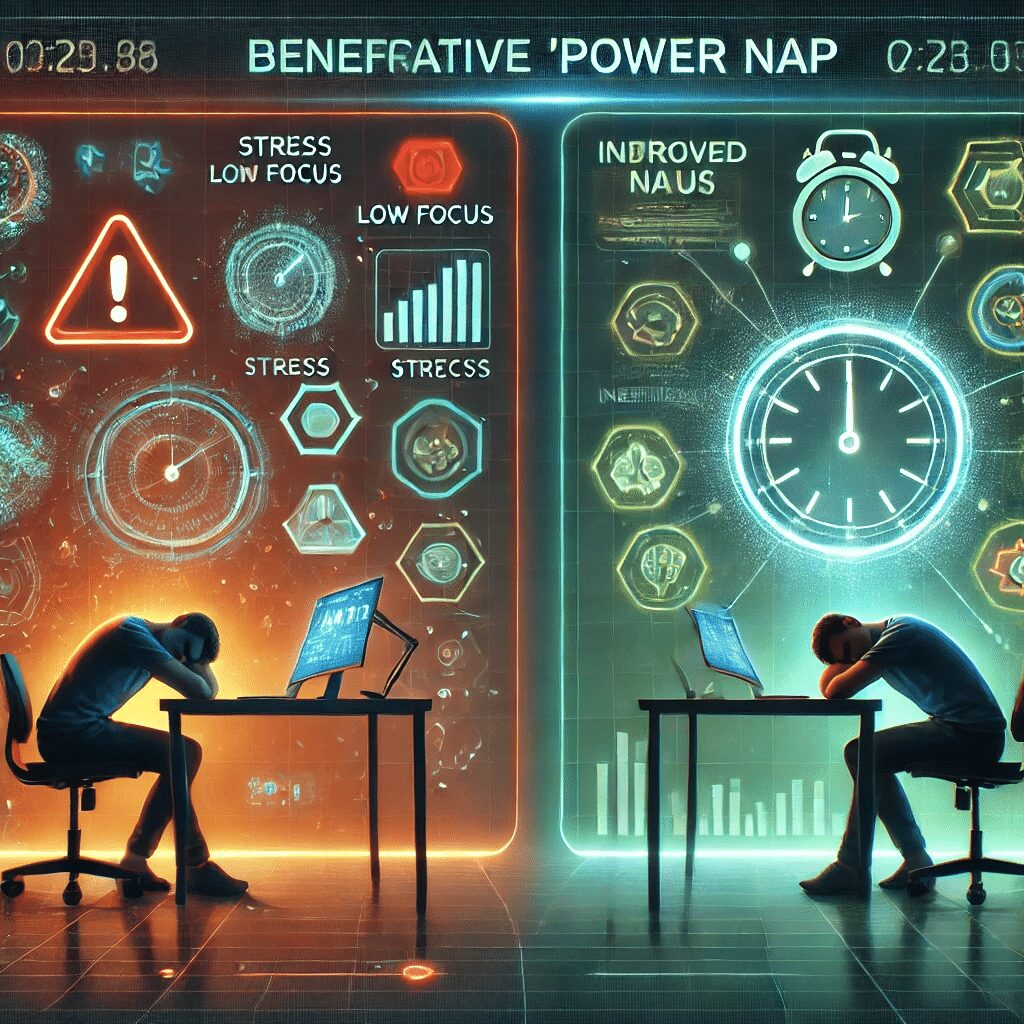
そこで効果を発揮するのが「パワーナップ」と呼ばれる短時間の仮眠です。
12時前後に15〜20分ほどの仮眠をとることで、午後のパフォーマンスが格段に向上するといわれ、この短い仮眠には脳の疲れをリセットし、注意力や記憶力を回復させる働きがあるのです。
パワーナップのやり方は非常に簡単で、椅子やソファなど横にならず軽く身体を休められる場所を確保し、15〜20分の間だけ目を閉じて休みます。
このとき、コーヒーや緑茶などに含まれるカフェインを仮眠の直前に摂取しておくと、20分後にはカフェインが作用し始め、自然とスッキリとした目覚めに導いてくれるのです。
これが「カフェインナップ」と呼ばれるテクニックで、仮眠の効果をさらに高める工夫のひとつです。
ただし、仮眠をとる時間帯には注意も必要で、午後3時以降に仮眠をとってしまうと、夜の本来の睡眠に影響を与えるリスクがあります。
睡眠の浅い方や不眠傾向のある方は、午後の遅い時間に寝てしまうと入眠が遅れ、睡眠リズムが乱れてしまうことも。そのため、仮眠は午後3時までにとどめるのが理想となっていきます。
また、仮眠の時間が30分以上になると、深い睡眠に入りやすくなり、起きたときに「頭がぼんやりする」「だるい」といった状態(睡眠慣性)に陥ることもあるため、あくまで短時間で切り上げることがポイントです。
 |
まとめ
快眠を得るために大切なのは、特別な方法ではなく、毎日の小さな習慣の積み重ねです。
朝の光を浴びることから始まり、日中に体を動かし、夜は心と体を落ち着ける時間をつくり、この自然なリズムが整うことで、眠りの質は確実に変わっていきます。
寝室の環境やお風呂の入り方、カフェインやスマホとの付き合い方など、少し意識するだけで、眠りはぐっと深くなります。
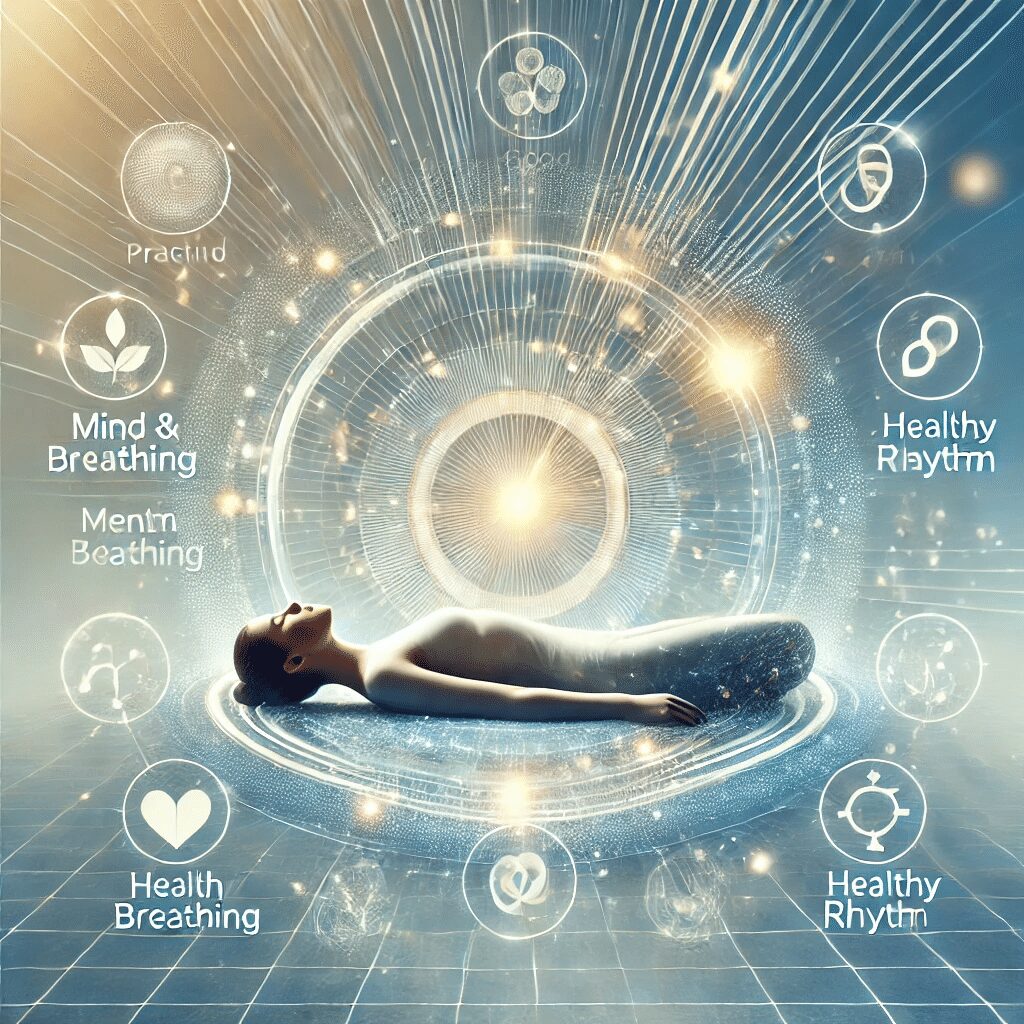
眠れない夜が続くときも、焦らず、自分のペースで改善していくことが大切です。
今日から一歩ずつ「快眠習慣」を実践し、心も体もリセットできる、本来の“休む力”を取り戻していきましょう。

最後まで見ていただきありがとうございました。
↓終活で分からない事や迷子になったら↓
このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています
LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV
インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/
アマゾンで本を出品しています

 |
- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方
- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

32




コメント